
地震保険の加入率が低いと聞きき、私もやめたいと考えているのですが、地震保険をやめた場合のデメリットってありますか?
この記事では、地震保険をやめたい方のために、地震保険をやめることで起こりうるデメリットについて詳しく解説しています。
私、個人的には、地震保険は必要だと思っています。
ただし、補償内容については、私自身もあまり納得がいくものではないと考えています。
日本は地震大国です。
日本には、2000もの断層があると言われています。
しかし、その2000もの断層は今現在、目に見えているもので確認できているものだけです。
実は、今、建物が建っている場所は確認する術がなく、この2000もの断層の中にはカウントされていません。
直近10年(2011~2021年)で地震保険金の支払いが多かった順にピックアップしました。(参考:損害保険料率算出機構 )
| 地震名など | 発生日 | 規模 (マグネチュード) |
|---|---|---|
| 平成23年東北地方太平洋沖地震 | 2011/3/11 | 9.0 |
| 平成28年熊本地震 | 2016/4/14 | 7.3 |
| 大阪府北部を震源とする地震 | 2018/6/18 | 6.1 |
| 平成30年北海道胆振東部地震 | 2018/9/6 | 6.7 |
| 宮城県沖を震源とする地震 | 2011/4/7 | 7.2 |
| 鳥取県中部を震源とする地震 | 2016/10/21 | 6.6 |
| 静岡県東部を震源とする地震 | 2011/3/15 | 6.4 |
| 福島県浜通りを震源とする地震 | 2011/4/11 | 7.0 |
| 長野県中部を震源とする地震 | 2011/6/30 | 5.4 |
| 胆振地方中東部を震源とする地震 | 2019/2/21 | 5.8 |
もちろん、この他の地震でも地震保険金の支払いはありますが、ここでは特に支払件数や支払金額が多いものを掲載しました。
この表を見ると、10年で10件、大きいものだけでも1年に1件の割合とは、日本の国土が地震と共存の上、成り立っているとしみじみ感じます。
にもかかわらず、「地震保険をやめたい」と考えている人も少なくありません。
そこで、この記事では、地震保険の加入率が低い理由も解説し、そこから見える地震保険をやめた人が陥るデメリットを探ってみたいと思います。
- 地震保険の特徴や補償の範囲
- 地震保険の加入率が低い理由
- 地震保険未加入のメリット・デメリット
この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
スポンサーリンク
地震保険の概要

まずは地震保険について、ざっと見ていきましょう。
地震保険の対象と補償内容
地震保険は、地震や噴火・(地震や噴火による)津波を起因として、建物や家財などが損害を被った場合に保険金が支払われる保険です。

ここで気を付けたいのが、地震が原因で起きた火災は、地震保険でしか補償されません。
つまり、地震が原因の火災は火災保険の対象外ということですね。
地震保険の対象は、
- 居住用の建物(店舗併用住宅は可)
- 家財
になります。
ただし、下記のものは保障の対象外になります。
- 門・塀・垣のみに生じた損害
- 地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害
- 損害の程度が⼀部損に至らない損害
- 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう
- 通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手
- 自動車 など
地震保険の補償内容は以下のとおりです。
| 損害の状況 | 損害の認定基準 (建物) |
損害の認定基準 (家財) |
支払われる保険金の額 |
|---|---|---|---|
| 全損 | 建物の時価の50%以上 建物の延床面積の70%以上 |
家財の時価の80%以上 | 地震保険金額の100% (時価額が限度) |
| 大半損 | 建物の時価の40%以上50%未満 建物の延床面積の50%以上70%未満 |
家財の時価の60%以上80%未満 | 地震保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 建物の時価の20%以上40%未満 建物の延床面積の20%以上50%未満 |
家財の時価の30%以上60%未満 | 地震保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水 |
家財の時価の10%以上30%未満 | 地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
ここでのポイントは、地震保険金額です。
地震保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決定します。
ただし、限度額があり、建物は5,000万円、家財は1,000万円です。
また、1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円です。(2021年12月10日現在)(参考:地震保険制度の概要 : 財務省)
万が一、この額を超える被害が発生したときには、被害の実態に即し、適時適切に政策判断が行われるものとされています。
地震保険の加入条件
地震保険は居住用住宅(併用住宅含む)であれば加入できますが、加入条件として、火災保険に加入していないと入れません。
地震保険は火災保険の特約です。
なので、地震保険だけの加入とか、火災保険はA保険会社、地震保険はB保険会社ということはできません。
また、事業用建物も加入できません。
地震保険料
地震保険料は、同じ条件であればどの保険会社と契約しても同じ保険料です。
大きな損害が発生してしまう地震が来た場合、保険会社だけでは保険金が払えないこともあるので、政府が再保険として地震保険を支えています。(これを「半公共的保険」といいます。)
政府が関与しているので、1回の地震で最高12兆円も保険金が払える仕組みが確保されているんですね。
保険料は、都道府県別・建物の構造別で算定されています。
東京は、鉄骨・コンクリート造は年間27,500円、木造42,200円です。
福岡は、鉄骨・コンクリート造は年間7,400円、木造12,300円です。
都道府県で保険料がちがうのは被害の大きさを考慮にいれています。
鉄骨・コンクリート造と木造の違いも被害の多さを考慮に入れています。
他の都道府県については、後述しています。
地震保険の加入率

ところでみなさん、地震保険の加入率はどの位だと思いますか?
調べてみたら、地震保険の加入率はたったの33.9%(2020年)でした。

上の表を見て頂くとわかるように、微増ではありますが上昇していますが、数字的にはびっくりするほど少ないんです。
私のまわりには地震保険をかけていない人の方が少ないので、不思議に思い、都道府県別の地震保険の加入率を調べてみました。
| 都道府県 | 2009年度 加入率 |
2019年度 加入率 |
差額 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 19.4% | 26.7% | 7.3 |
| 青森 | 14.5% | 22.5% | 8.0 |
| 宮城 | 32.5% | 52.0% | 19.5 |
| 福島 | 14.1% | 31.8% | 17.7 |
| 東京 | 30.0% | 37.3% | 7.3 |
| 神奈川 | 28.3% | 36.4% | 8.1 |
| 山梨 | 23.8% | 34.7% | 10.9 |
| 長野 | 12.1% | 24.8% | 12.7 |
| 静岡 | 24.4% | 32.3% | 7.9 |
| 愛知 | 34.5% | 43.0% | 8.5 |
| 京都 | 19.6% | 33.8% | 14.2 |
| 大坂 | 24.4% | 35.6% | 11.2 |
| 兵庫 | 18.4% | 31.0% | 12.6 |
| 島根 | 11.2% | 19.2% | 8.0 |
| 山口 | 17.4% | 27.9% | 10.5 |
| 福岡 | 26.1% | 37.6% | 11.5 |
| 長崎 | 10.2% | 18.8% | 8.6 |
| 熊本 | 22.2% | 42.8% | 20.6 |
| 沖縄 | 9.5% | 16.6% | 7.1 |
主なところをピックアップしました。
宮城や熊本など大きな地震があった県は加入率も大幅にアップしています。
一方、近隣の県は意外に低いのには少しびっくりしました。
また、直下型地震がくると言われている東京も加入率がそんなに高くないですね・・・。
だからと言って、地震への脅威がないというわけではありません。
地震保険加入率が低いのには理由があります。
- 補償対象が「一部損」以上でないと補償されない
- 全壊した場合でも最大火災保険の半額しか補償されない
- 地震保険料が高い
それでは1つ1つ見ていきましょう。
加入率が低い理由①
補償対象が「一部損」以上でないと補償されない
地震保険は一部損以上でないと補償されません。
一部損とは、居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁はり・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の3パーセント以上20パーセント未満のことを言います。
例えば、火災保険では、「塀」などの建物の主要部分でないところでも保険金が支払われますが、地震保険の場合は保険金は支払われません。
加入率が低い理由②
全壊した場合でも最大火災保険の半額しか補償されないい
建物が全壊し、「全損」認定されても、最高で火災保険の半分しか地震保険はもらえません。
さらに地震保険金額の100%補償される場合でも、下記のような上限枠があります。
- 建物・・・5,000万円
- 家財・・・1,000万円
これでは、地震前と同じような建物は建たないので、地震保険に加入するメリットをあまり感じられませんね。
加入率が低い理由③
地震保険料が高い
地震保険料は、都道府県や建物の構造で変わってきますがここでは代表的なものをピックアップしました。(地震保険料は、2021年1月1日から改定されています。)
今回算出した地震保険料の前提条件は以下のとおりです。
- 地震保険期間:1年
- 地震保険金額:1,000万円あたり
- 割引き適用なし
- 一括払い
- イ構造・・・主として鉄骨・コンクリート造
- ロ構造・・・主として木造
| 都道府県(加入率) | イ構造 | ロ構造 |
|---|---|---|
| 北海道(26.7%) | 7,400 | 12,300 |
| 宮城県(52.0%) | 11,800 | 21,200 |
| 福島県(31.8%) | 9,700 | 19,500 |
| 東京都(37.3%) | 27,500 | 42,200 |
| 長野県(24.8%) | 7,400 | 12,300 |
| 静岡県(32.3%) | 27,500 | 42,200 |
| 愛知県(43.0%) | 11,800 | 21,200 |
| 大阪府(35.6%) | 11,800 | 21,200 |
| 福岡県(37.6%) | 7,400 | 12,300 |
| 熊本県(42.8%) | 7,400 | 12,300 |
| 沖縄県(16.6%) | 11,800 | 21,200 |
この表を見ると、東京や静岡県など危険地帯でも加入率が低いのは、地震保険料が高いことが原因の1つであると考えられます。
東京の木造住宅に住んでいる方では、地震保険金額1000万円の掛金に対し、年間42,200円を払うことになります。
10年払い続けると422,000円ですか・・・。高いですね・・・。
地震保険料だけでは元の生活と同水準に戻れないのに、この金額は少し躊躇してしまいますね。
地震保険に加入しない場合や地震保険をやめたときのメリット・デメリット
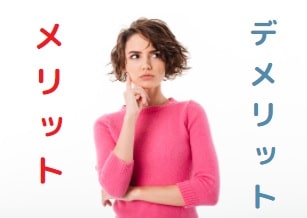
地震保険に加入しない場合や地震保険をやめた場合は、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
地震保険に加入しないメリット
地震保険をやめる(加入しない)場合のメリットは、ただ1つ、地震保険をかけない分、火災保険料が安くなることです。
先程も見て頂いたとおり、地震保険料は高い場合がほとんどで、家計の負担になることもあり、やめたい(加入しない)方も多いかと・・・。
ただし、その決断は、次にご紹介するデメリットをよく検討の上、下すことをおすすめします。
地震保険に加入しないデメリット
デメリットは大きく分けると次の3つになります。
- 地震で家屋が壊れたり火災にあったりしても保険金がもらえない
- 住宅ローンが残っている人は2重ローンになる可能性がある
- 地震保険料控除を受けることができない

それぞれ詳しく見ていきましょう。
デメリット①
地震で家屋が壊れたり火災にあったりしても保険金がもらえない
地震を起因とした火災は「火災保険適用外」です。
また、地震で家屋の倒壊や修理が必要になった際も、保険金はもらうことができず、自費での立て直しになります。
特に、家屋が使い物にならなければ、家屋の撤去費用も必要になってきます。
もちろん公的支援もあります。また、被害が甚大になれば、それなりに支援も増えるでしょう。
とは言え、テレビなどで皆さんもご存知のように、それだけではとても足りません。
地震保険の保険金は当面の生活に必要な資金として使うことができますが、地震保険に入っていなければ、保険金はもらえないので、自力でどうにかする必要があります。
苦しいときこそ、臨時の収入はとてもありがたいものです・・・。
デメリット②
住宅ローンが残っている人は2重ローンになる可能性がある
家屋が倒壊しても住宅ローンの債務は消えません。
特に、新居を住宅ローンで購入した方が、また新居を購入(建て直す)場合は、2重ローンに苦しむことになります。
地震保険の加入を考えていない人も、住宅ローンが残っている間は地震保険に入っておくことをおすすめします。
デメリット③
地震保険料控除を受けることができない
地震保険に入っていれば、地震保険料控除を受けることができ、所得税と住民税の節税効果が狙えますが、加入していなければその控除を受けることができません。
地震保険料を安く抑える方法

地震保険は、どの保険会社で契約しても保険料は変わりません。
そんな地震保険ですが、実は安く契約することができます。
ここではその方法をご紹介しましょう。
- 割引制度を活用する
- 一括払いをする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
地震保険を安くする方法①
割引制度を活用する
地震保険は、一定の基準に基づく耐震性能を備えた建物については4つの割引制度があり、いずれか1つ選択することができます。
| 割引率 | 概要 | |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 50% | 住宅性能表示制度の「免震建築物」に該当する場合 |
| 耐震等級割引 | 等級に応じ10%・30%・50% | 住宅性能表示制度の「耐震等級1・2・3」に該当する場合 |
| 耐震診断割引 | 10% | 耐震診断・耐震改修により、現行耐震基準を満たしている場合 |
| 建築年割引 | 10% | 1981年6月1日以降に新築した場合 |
地震保険を安くする方法②
一括払いをする
一括払いをした場合も通常よりも安く地震保険に加入することができます。
| 地震保険期間 | 長期係数 |
|---|---|
| 2年 | 1.9 |
| 3年 | 2.85 |
| 4年 | 3.75 |
| 5年 | 4.65 |
例えば、東京都にある鉄筋コンクリート造の建物の地震保険を、5年一括で支払った場合と1年更新を5回繰り返した場合を見てみましょう。
差額は5年間で9,625円。1年に換算すると1,925円お得になります。
とは言え、まだまだ高いので、主契約である火災保険の方で少しでも安い取扱保険会社を選ぶのが一番です。
実は、火災保険料も年々上がっています。
特に、2022年10月からの値上げは非常に大きいものになると予想されています。(詳しくは「【火災保険10年廃止はいつから?】2022年10月火災保険値上げで過去最大の負担増! 」で記載しています。)
ですが、火災保険は、同条件でも取扱保険会社によって火災保険料が違うため、比較検討することで安くすることができます。
火災保険料を比較する方法は2つあります。
1つは火災保険を一括見積もりする方法です。
おすすめのサイトは以下のとおりです。
サイト名をクリックすると公式HPにアクセスすることができます。
| 住宅本舗 |
|||
|---|---|---|---|
| 見積数 | |||
| 公式HP |  |
 |
建物の情報を入力すると、複数社の火災保険の見積りをしてくれます。
詳しくは下記に記載しています。
ただ、どうしても建物情報などは自分で入力する必要があります。
ガイダンスに沿って入力すれば簡単に見積もりが出せますが、そういった手間を省きたいのであれば、2つ目の手段として、無料で相談にのってくれる無料保険相談窓口があります。
無料保険相談窓口では、今入っている火災保険証書などを見て、FPがいい保険を探してくれるので簡単に比較できます。
ここではおすすめの保険相談窓口をピックアップしました。
|
保険見直しラボ
|
保険見直し本舗
|
保険マンモス
くわしく見る |
保険のトータル
プロフェッショナル |
保険ガーデン
|
みんなの生命保険
くわしく見るアドバイザー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗相談 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 訪問サービス | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| オンライン相談 | ○ | ○(電話相談も可) | - | - | - | - |
| 生命保険 | ○(21社) | ○(24社) | ○(店舗による) | 派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
| 損害保険(火災保険) | ○(11社) | ○(13社) ※ペット保険2社含む |
- | 派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
| 公式HP | 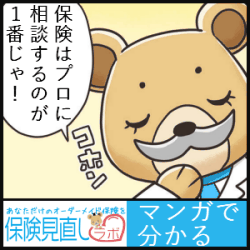 |
 |
 |
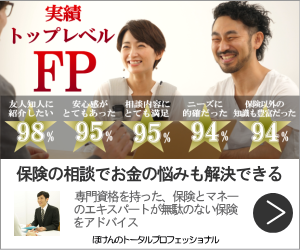 |
 |
こちらからすぐに相談を申し込めるので、気になった保険窓口相談があったら申し込んでみて下さいね。
保険の窓口についてはこちらの記事を参照して下さい。
まとめ:地震保険はいざという時のためにぜひ加入を!

地震保険は確かに高いと言わざるを得ません。
とは言え、実際に被害が甚大な地震が起きた際は、保険金がない人とある人の精神的なダメージは全然違います。
苦しい時こそ、金銭的に多少でも救いがあれば、精神的にも少し楽になるのではないでしょうか。
家が倒壊しても余裕で暮らせるだけの蓄えがある方は、地震保険は不要と言えますが、それ以外の人は、加入することをおすすめします。
そもそも、保険はほとんどの方が「損」をします。
逆に、保険で「得」をしている方は、それ以上の「不幸」に見舞われている方です。
なので、保険金が下りないような地震に合わなければ、「地震保険で損した」と考えず、「人生得した」と思うようにすると、地震保険について、もっと前向きになれるのではないでしょうか?
特に、住宅ローンを抱えている方やお子さんがいる方、また、持病がある方は、少し無理をしてでも地震保険に加入することをおすすめします。
災害弱者になる可能性がある方も同様です。
どうしても家計が厳しいようであれば、火災保険を見直すことも検討しましょう。
火災保険は、意外に保険対象になる事象があります。
火災保険の時効は3年です。地震保険の加入を検討する際は、火災保険の請求漏れのないか、見直してみるのもいいですね。
火災保険については下記で詳しく記事にしています。
>>【家財保険】わざと壊した場合も申請できる?|家財保険の裏ワザも紹介
>>【読めば簡単解決!】火災保険の選び方|ブログならではの体験談あり
>>【火災保険で儲けることはできる?】儲かる人と損する人の違いを解説!











