
火災保険の請求をしたいのですが、自分でできますか?
誰に聞いたらいいかもわかりません。
この記事ではこんなお悩みにお答えします。
まずは結論から。
さらに修理業者や保険会社のアドバイスを聞けば、より簡単に請求できます。
実際、私は台風被害で過去2回火災保険を請求し、火災保険金を請求額満額頂きました。
基本、私はよりいい結果を導くため、業者とのコミュニケーションをいつも大事にしています。
そこで得た知識やコツを余すことなくお伝えしていきます。
火災保険補償対象の事故にあってから3年間(保険法95条)
過去に修理してしまったものも、もしかしたら火災保険請求できるかもしれないのであきらめないで下さいね。
- 火災保険の請求方法
- 火災保険の請求する際のコツ
この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
スポンサーリンク
火災保険の請求ができるケース

火災保険の申請ができるケースはご自身が加入している火災保険契約によりそれぞれ違います。
主なものは次の通りです。

火災保険は、自分で補償対象を選んで加入します。
主な補償内容は、火災・落雷・風災などがあり、その他、水災、物体の落下・飛来・追突など、破裂・爆発、雹(ひょう)災・雪災・飛来・騒音・盗難なんていうのもあります。
火災保険の申請は、契約時に選択した補償に対して行うことができます。(選択した補償がわからない場合は、火災保険証券か保険会社に問い合わせればすぐにわかります。)
ただし、火事でも地震に起因した火事は、火災保険の補償の対象外です。
地震で発生した火事は「地震保険」で補うことができます。
火災保険の請求方法|流れと請求のコツ(ポイント)は?

火災保険の請求の流れは以下のとおりです。
この行程はあくまでも理想形なので、多少前後することもあります。
もちろん、屋根が壊れて緊急に工事をするなど、先に修理をしても火災保険金はもらえますので安心して下さい。
先に工事をする場合でも必ず破損個所の写真だけは撮影しておいてくださいね。
ただ、先に修理してしまうと、保険金がもらえない場合や減額された場合は自腹での工事になります。
ですので、急を要しない修理の場合は保険金が振り込まれてから工事するのがベストです。
ここでは、保険請求する上で、後悔しないためのちょっとしたコツもお伝えします。
それでは一連の流れを詳しく見ていきましょう!
ステップ①
被害状況の確認
まずは被害状況の確認をしましょう。
その際、必ず、写真を撮っておきましょう。
写真はできれば日付入りがいいですが、今は日付も加工ができてしまうことから、証拠書類としては若干弱い部分もあるため、できれば、手帳に被害状況などを記載しておきましょう。
写真は、できるだけ多く撮影しておいて下さい。
撮影のコツは、まずは建物全体像、そして全体像から見た被害(破損)箇所、もう一つ、被害部分を拡大した写真の3種類撮影しておくといいでしょう。
- 写真は①全体像②全体から見た被害部分③拡大した被害部分の3種類撮影する
- 写真はできるだけ多く撮影しておく
ステップ②
保険会社に連絡
次に保険会社に連絡します。
その際はお手元に火災保険証書と先程撮影した写真を用意しておくとスムーズに話が進みます。
もし、業者で知り合いがいれば、先に修理の相談をしてから保険会社に電話するのもありです。
なぜなら、業者さんは意外に保険請求に詳しく、アドバイスをくれる場合があるからです。
業者さんとのコミュニケーションで思わぬ情報が手に入ることもありますよ。
こちらからの被害の説明をすると、保険会社さんが補償の対象になりそうかどうか判断し、対象になりそうであれば、保険請求に必要な書類を一式、郵送してくれます。
電話で説明があると思いますが、保険請求するにあたり、必要となる書類をキチンと聞いてメモしておきましょう。
- 火災保険証書と被害を撮影した写真を手元に置いて電話する
- 知り合いの業者がいれば先に相談しておくことがベスト
- 必要書類の確認をする
ステップ③
役所に連絡
ステップ②で「罹災証明書」が必要と言われた場合は役所に電話し、罹災証明書の発行の仕方を聞いて下さい。
私は2回台風の風災での火災保険金を請求しましたが、被害額が少額(30万円前後)だったためか、その台風での保険金請求が多い時期だったためかはわかりませんが、「罹災証明書」は必要ありあせんでした。
もし罹災証明書が必要であれば必ず取得して下さい。
ステップ④
業者へ連絡
ステップ②で火災保険が申請できそうであれば、業者へ連絡しましょう。
一刻も早くというのであれば、保険会社に連絡する前に業者へ連絡するのもありです。
ただし、その被害が補償対象外のこともあり得ますので、ご注意下さい。
業者さんへは相見積を依頼することをおすすめします。
保険の請求は、その見積書をもって金額が決定します。
仕事が欲しいばかりに安い見積書を出し、工事中にどんどん費用を追加してくる業者も一定数います。
そんな場合でも、保険金は追加分の費用はもらえません。
逆に、今以上のグレードの工事の見積を出してくる業者もいます。
例えば、台風で窓ガラスが割れ保険請求をする際は同じグレードの窓ガラス分しか保険金が下りません。
そこに工事業者が窓にシャッターを付けた工事費用の見積もりを出してきてそのまま保険請求してもシャッター部分の工事費と材料は減額されます。
つまりもし、シャッターを付けるのであれば自腹になります。
自腹覚悟でお願いするのであればいいのですが、「保険金でシャッター付窓を付けることができる!」と勘違いしても、後の祭りですので気を付けてください。
また、見積書は明細がキチンとした業者を選びましょう。「改修工事一式○○円」という業者は要注意です。
- 見積もりは相見積がおすすめ
- 見積書がキチンとした業者さんがおすすめ
- 必要な費用はキチンと保険金で補填してくれるので「安かろう」の業者は選ばない(逆にグレードが上がる工事見積もりは保険金給付が減額されるので注意!)
- 業者さんとのコミュニケーションを大事にする(思わぬ情報が手に入ることも)
ステップ⑤
保険会社へ書類を提出
資料がそろったら保険会社さんに書類を提出しましょう。
提出書類は、火災保険会社に連絡した際にきちんと聞いて下さい。
ここでは主な提出書類を列挙しました。
保険会社や修理金額により提出書類が違ってきますので、保険会社に必ず確認して下さい。
私が台風の風災で保険金請求した際は罹災証明書は提出を求められませんでした。
保険金請求書には、外観の見取り図を記載し、どこの部分に修理が必要かを明記して、その部分の写真を貼付したりしました。
見取り図は正確な縮尺でなくてももちろんOKです。
わかりやすさを優先しましょう。
わかりやすく書くこと、そして被害状況がわかりやすい写真を提出することで、保険金請求がスムーズに進みます。
そこがちょっと面倒ですが、あとは簡単に処理できましたので安心して下さい。
ちなみに写真は、工事業者も撮影していますので、そのデータを印刷してもらってそれを提出するのもアリです。
- 外観見取り図や修理が必要な場所の記載はわかりやすく書く
- 被害がわかりやすい写真を貼付する
ステップ⑥
保険会社の調査及び連絡
保険会社に保険金請求書届いたら、その書類を元に審査されます。
保険会社には修理工事の各種データがあり、そのデータと照らし合わせて、その申請額が適正かどうかを判定します。
通常の工事よりも請求額が多い場合や、グレードアップ工事が含まれていると判断した場合、または事故原因が補償内容とは違うなどの判断がされた場合は減額、もしくは支給がされないこともあります。
「保険金でいい家がたった」と思われることもありますが、保険金が新価(再調達価格)以上にでることはありません。
>>【火災保険で儲けることはできる?】儲かる人と損する人の違いを解説
また、保険金支給判断の際に「鑑定人」が派遣されることもあります。
条件は一概には言えませんが、保険請求額が大きいとその分、鑑定人がくる可能性が上がります。
鑑定人は、損害があった建物や家財の調査、損害額の妥当性を調査します。
鑑定人の中には、火災保険会社に肩入れし、「損害を認めない」方向でやってくる人もいます。
被害にあった箇所を否定され納得がいかなければ、毅然とした対応をおすすめします。
その鑑定に不満があるようであれば、鑑定会社を変えてもらいましょう。
それでも納得がいかないようであれば、損保ADRセンターに連絡することをおすすめします。(クリックすると公式HPへ飛びます。)
火災保険金請求からおよそ1ヶ月以内で保険金が振り込まれます。
甚大な災害が起きた時や災害が多い時は遅れる場合もあります。
実際、私が火災保険金を請求した時は、甚大な災害のときで、保険会社から「1ヶ月を超えるかもしれないがなるべく早く振り込めるようにします。」と、とても丁寧にご対応いただきました。
結果としては、20日かからないくらいに無事入金されました。
保険請求は、実際に被害を受けている方への対応なので、基本的にはとても親切に対応してもらえますので安心して下さい。
ステップ⑦
工事開始
保険金が支払われたら早速、工事開始です。
もちろん、保険金を受け取る前に工事を開始しても差し支えありませんが、万が一、補償対象外などの理由で、却下もしくは減額された場合は工事は自腹になります。
そもそも修理工事が必要だからこそ保険金請求をしています。
なので、却下になろうがなかろうが工事の必要性はあるので、先に工事するという選択肢はあるでしょう。
でも工事を始めてしまえば、当初の予定どうり工事が進んでしまいますが、まだ工事をしていなければ、予定を変更できます。
具体的には、減額された場合であれば(「工事費が通常よりも高い」ということなので)工事業者にもっと安く工事をするようお願いできます。
補償範囲外で却下ということであれば、再度、工事を見直し、金額を抑えた工事をするという判断も下せます。
待てるのであれば、保険金額が確定されるまで待ってから工事を始めるのが賢明です。
ステップ⑧
完成
工事が終了し完成したら、請求額を業者に振り込んで終了です。
基本的には、見積書通りの保険金額が入金されるので、その入金された金額をそのまま業者に移転します。
ただし、見積金額を少なく見積もった場合で、見積額よりも高くなった場合でも、追加の保険金請求はできません。
ですので、見積もりの時点できちんと金額をすり合わせましょう。
まとめ:火災保険の請求はコツ(ポイント)をつかめば失敗しないで簡単にできる

火災保険金請求は一見、難しそうに思えますが、実はとても簡単です。
とは言え、素人では見過ごしてしまう損害などもあります。
「プロに申請をお願いしたい」と考えている方は、「【怪しい・・・】火災保険申請代行サポートは違法じゃないの?|悪徳業者の見分け方 」で詳しく解説しているので確認してみて下さい。
すぐにでもお願いしたい方はこちらからでも確認できます。
【おすすめの火災保険申請サポート会社】
|
保険請求の窓口
|
お家のドクター.com
|
損害保険申請サポート
|
火災保険申請ドットコム
|
住まいる申請
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 50% | 39.8% (工事をしない場合のみ) |
40% | 38.5% | 27% |
| 実績 | 年間100件以上 | 年間1000件以上 | トータル13600件以上 | 年間1000件以上 | 年間3000件以上 |
| 対応エリア | 全国30ケ所以上 | 全国 | 全国 | 全国 (北海道一部と離島を除く) |
全国 |
| 保険金の使い道 | 自由 | 修繕工事の施工 (施工しない場合は上記手数料が発生) |
自由 | 自由 | 自由 |
| 法律事務所 の監修 |
あり(グローウィル国際法律事務所) | なし | あり | なし | あり |
| 公式HP |  |
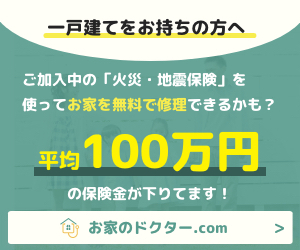 |
 |
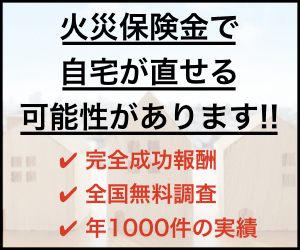 |
 |
これらの火災サポート会社については下記記事で詳しく説明しています。
火災保険は、そもそも損害が出た場合に備える保険なので、ちょっとでも被害にあったら、「これって保険がおりるんじゃないの?」と意識しておくといいでしょう。
また、家財保険も保険金がおりる場合が多いので意識してみて下さい。(詳しくは「【家財保険】わざと壊した場合も申請できる?|家財保険の裏ワザも紹介 」で記載しています。)
保険は何度も使えます。
困った時のための備えなので、ぜひ活用しましょう!











