
再婚して子供がいます。
前妻との子供に自分の遺産を相続させない方法はありますか?
できれば遺産相続で揉めないようにしておきたいです。
この記事ではこんなお悩みを解決します。
まずは結論から!
ただし「相続放棄」は非現実的
よって、前妻との子に少しでも財産がいかないように対策をするしか方法はない
前妻との子も後妻との間の子も、血のつながりがある以上、「相続権」は平等です。
なので、前妻との子だけを相続をさせないということはできません。
逆もしかり!
前妻の子だけに相続させることもできません。
本記事では、前妻との間の「子」にできるだけ相続させない方法を記載しています。
- 相続権の基本的な考え方
- 前妻の子への相続を最小限にする方法
この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
スポンサーリンク
遺産相続の大前提

まずは遺産相続を語る上で、大前提となっている
- 法定相続分
- 優先される遺産分割方法
- 遺留分
について見ていきましょう。
間違った認識をされている方もいらっしゃるので、ここは必ず確認して下さいね。
法定相続分について
法定相続分とは、民法に定められた相続割合のことをいいます。
民法では、 法定相続順位は、配偶者が常に権利があり、その他は次に掲げる第一順位から第三順位の順に権利が発生します。
| 法定相続人 | 相続割合 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子供1/2 |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 直系尊属1/4 |
- 子・直系尊属・兄弟姉妹は人数が増えれば、その割合をさらに平等に分割します。
- 配偶者がいない場合は、その他の相続人で平等に分割します。
例えば、妻と子2人の場合は、妻1/2と子は1/4づつになります。
妻と両親しかいない場合(つまり子がいない場合)は、妻2/3と両親が1/6づつとなります。
この他、代襲相続などがありますが、ここでは説明を省略します。
詳しくは、下記記事に分かりやすく具体例を出しているので、参考にしてみて下さい。
優先される遺産分割方法
遺産分割には、優先順位があります。
優先順位は以下のとおりです。
- 遺言書
- 遺産分割協議
- 法定相続分
『遺言書』があれば、遺言書に従わなければなりません。
ただし、遺留分を侵害されている人が「遺留分」を主張すれば、遺留分について分割する必要があります。(「遺留分」については後述します。)
次に優先されるのは、『遺産分割協議』です。
遺言書がなければ、相続人すべてが協議し、遺産の分配をします。(これを『遺産分割協議』といいます。)
遺産分割協議が難航すれば、『法定相続分』で分配します。
あれ?
遺産分割協議って、法定相続分で分けるんじゃないの?
みなさん、ここが勘違いするところですが、遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば、どのような分配にでもできます。
例えば、配偶者と子が2人いて、「すべて配偶者に」と相続人全員が了承すれば、すべて配偶者に遺産を渡すことができます。
遺産分割協議で「すべて寄付しよう」と相続人全員が了承すれば、すべて寄付もできます。
ただし、遺産分割協議ではお互いの主張がぶつかりますので、通常、『法定相続分』を目指して協議されます。
この遺産分割協議が上手くまとまらなければ、調停⇒裁判とどんどん発展しますが、これらも通常「法定相続分」を目指して解決策を模索していきます。
遺産分割は「法定相続分」でしなければならないと思われている方がいますが、法定相続分は最終手段になります。
遺留分について
遺留分とは、法定相続人が最低限の権利として一定額まで遺産を取得できる権利をいいます。
遺留分が認められる人は兄弟姉妹以外の法定相続人です。(これを「遺留分権利者」といいます 。)
遺留分は法定相続分の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の1/3)となります。
2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することになりました。
わかりやすい例で言えば、相続人が妻しかいない被相続人が遺言書に「全財産を愛人に渡す」と記載しても、妻には全遺産の1/4(1/2の1/2)を請求する権利が与えられています。(子がいれば、子の法定相続分の1/2を請求する権利が与えられます。)
前妻との子に相続させない方法

前妻は相続人にはなりませんが、前妻との「子」には、後妻との「子」と同等の相続権があり、法定相続人になります。
なので、前妻との子を抜きにした遺産分割協議は法的に無効になりますので注意して下さい。
逆に、後妻の連れ子には、どんなに親密な関係が築けていても相続権はありません。
財産を築き上げるために後妻の協力が多かったとしても、後妻の連れ子が老後の面倒をみてくれても、対策も練らなければ、後妻の連れ後には相続権がありません。
【関連記事】再婚相手の連れ子への相続はどうなる?|相続させたい場合の対策もあり!
それでは早速、前妻の子に相続させない方法を見ていきましょう!
- 遺言書を書く
- 生前贈与をする
- 相続放棄をしてもらう
- 遺留分を放棄してもらう
- 生命保険を活用する
これらの方法には、デメリットも存在します。
なので、いくつかの方法を組み合わせて対応していくのがいいでしょう。
ここでは、それぞれの方法とそのデメリットに対する対策も詳しく解説していきます。
前妻との子に相続させない方法①
遺言書を書く
遺言書は遺産分割において最優先されます。
よって、遺言書を作成しておくことは、相続トラブルが少なくなるという点でも最適な方法です。
ただし、遺言書は法律にのっとって記載しないと「無効」になる恐れもあります。
また、「後妻とその子に全部遺産を渡す」などの記載では、前妻との子の遺留分が担保されず、結果、遺留分侵害額請求される可能性が高くなります。
- 法律にのっとった遺言書を作成する
- 遺留分侵害を考慮に入れた遺言書を作成する
- 弁護士などの専門家に相談する
前妻との子に相続させない方法②
生前贈与をする
前妻との子に相続させない方法として、後妻との子や連れ子に、あらかじめ生前贈与しておくのも1つの手です。(これを「特定受益」といいます。)
ただし、特定受益には時効がありませんので、遺産分割協議の際は、生前贈与したものも遺産に含まれ協議が行われる可能性があります。
その場合、生存贈与された人は、前もって遺産を分けてもらったということになり、被相続人の死後の相続財産が少なくなる可能性があります。
一方で、遺留分の請求に関しては「特定受益」に対して時効があります。
時効は10年。
つまり、10年以上前の「特定受益」に関しては、遺留分の請求があっても考慮されません。
生前贈与する場合には早めの行動が一番ですね。
- 遺留分侵害を考慮に入れた遺言書を作成する
- 生前贈与は早めに行っておく(ただし、通常の遺産分割には特定受益の時効がないので注意!)
前妻との子に相続させない方法③
相続放棄をしてもらう
相続放棄をしてもらうのが一番の早道ですが、よっぽどのことがない限り、これは難しいと思います。
相続においては、仲のいい兄弟でも揉めることが多いのが現状ですので、前妻との子においては、「相続放棄」という話を持っていくのはトラブルの元になりかねません。
相続トラブルについては下記で詳しく記載しています。
また、皆さん誤解をされている方が多いですが、相続放棄をすることができるのは「相続の開始を知ったときから3ヶ月まで」です。
つまり、「生前には相続放棄はできない。」ということですね。
いくら生前に相続放棄を約束していても、何かのきっかけで気持ちが変わることも十分ありうるので、この方法はおすすめしません。
【関連記事】相続放棄の失敗例やメリット・デメリットを詳しく解説
前妻との子に相続させない方法④
遺留分を放棄してもらう
相続放棄は被相続人の生前はできませんが、遺留分を有する相続人が相続の開始前(被相続人の生存中)に家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
手続きについては、裁判所のHP「遺留分放棄の許可 | 裁判所」でご確認下さい。
ただし、遺留分の放棄が認められるのは、遺留分権利者に放棄の対価を提供されているか」が問題となります。
例えば、生前に結婚資金やマイホーム費用の援助などを受けていることがあれば許可されます。
つまり、なんらかの援助や対価の提供は必要だということになります。
前妻との子に相続させない方法⑤
生命保険を活用する
死亡保険金は契約形態により、受取時に受取人個人の財産になります。
つまり、死亡保険金受取時には「相続財産に含まれない」ということですね。

この取扱いを利用し、後妻との子を受取人にした生命保険金に加入すれば、相続財産を少なくできます。
例え、前妻との子が遺留分を主張しても、生命保険金はそもそも相続財産とはならないので、そもそも「遺留分」は存在しません。
また、この方法によれば、後妻の連れ子と養子縁組をしなくても、連れ子に遺産を分けてあげることができます。
ただ、養子縁組をしていなければ、連れ子の税金が少し高くなるのがデメリットとしてあげられます。
相続で加入すべき生命保険については、税金の話を含め、下記で記載しています。
こういった保険に加入する前には、必ず、専門家に相談して下さい。
今では、無料で保険相談にのってくれるところがあります。
自宅で相談もできますし、自宅で相談しづらい場合は、店舗や喫茶店でも相談にのってくれるのでおすすめです。
ここではおすすめの保険相談窓口をピックアップしました。
|
マネードクター
|
保険チャンネル
|
保険見直し本舗
|
保険見直しラボ
|
保険マンモス
くわしく見る |
保険ガーデン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗相談 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 訪問サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○(電話相談も可) | ○ | - | - |
| 生命保険 | ○(22社) | ○(14社) | ○(24社) | ○(21社) | ○(店舗による) | 派遣される FPによる |
| 損害保険 | ○(10社) | ○(14社) ※ペット保険2社含む |
○(13社) ※ペット保険2社含む |
○(11社) | - | 派遣される FPによる |
| 公式HP | |
 |
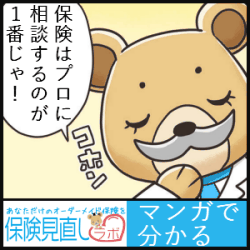 |
 |
 |
こちらからすぐに相談を申し込めるので、気になった保険窓口相談があったら申し込んでみて下さいね。
保険の窓口についてはこちらの記事を参照して下さい。
相続については特に専門性が高いので、相続に詳しいFPが多く在籍しているマネードクターがおすすめです。
<公式>マネードクター
その他の無料保険窓口にもそれぞれ特徴があります。
です。
相談相手はできる限り自分と同じ境遇、または話しやすい人がいいですよね。
そんなこだわりがある方は、保険チャンネルがおすすめです。 ![]()
まずは気軽に相談したい方は、保険の相談ができる【アプリ】があります。
★保険の見直しには下記アプリで簡単にアドバイスがもらえます。
\ 無料で診断! /
- 何回でも利用可
- 住所・氏名・電話番号などの個人情報不要
- 希望があれば相談にものってもらえる
パシャって保険診断については下記で詳しく記載しています。
まとめ:相続は前妻との子抜きには話を進められないので前もって対策を!

前妻との子は、離婚から何年たとうが、絶縁状態であろうが、相続人であることは変わりありません。
相続人である以上、被相続人の遺産分割協議の際は、「前妻との子」抜きでは話し合いができません。
例え、「前妻との子」抜きで話し合いをし、相続財産を分けてしまっても、法的には無効なので、遺産分割協議のやり直しが求められます。
万が一、すでに遺産を使い切ってしまったとしても、前妻との子が求めれば、法定相続分の財産を引き渡す義務が生じます。
通常の遺産相続でも揉めるケースが多い中、前妻との子が入れば、通常はトラブルも増えます。
逆に、「前妻との子には何もしてあげられなかたっので少し多めに財産をあげたい」とか「後妻の連れ後にも自分の子達と同等の財産をあげたい」などの希望があれば、より一層対策を立てるのが賢明です。
対策を立てる際は弁護士に相談するのがおすすめです。
「弁護士に相談するほど財産がない」と言う方は、市区町村などで無料の相談にのってもらえます。
弁護士については下記で詳しく解説しています。
相続人が増えれば増えるほど、トラブルはつきものです。
そのトラブルを減らすことができるのは、被相続人だけです。
ぜひ、早めの対策でできる限りトラブルを回避しましょう。
- 保険相談はどこがいい?|相談相手別のメリット・デメリットを解説
- 【遺産相続】相続税っていくらまで無税?|いくらから税金かかるの?
- 相続税は自分で申告しない方がいい理由と税理士の選び方6選
- 【注意】110万以下の贈与でも非課税にならない場合がある!
- 【嫁・婿への相続】マスオさんが波平さんの遺産を相続するには?
- 「必要な保険は3つだけ」は本当?|最低限入っておくべき保険と理由を解説
- 【保険の窓口にカモられるかも!?】騙されないための7つの方法
- 【医療保険に入らないと後悔する人は?】「もったいない」という不要論についても検証!
- 【無料保険相談のカラクリを暴露】 利益の構造(からくり)を知ってかしこく相談!
- 【保険見直し本舗のデメリット5つ】「しつこい」って評判は本当?|ほけんの窓口との比較も掲載















