
火災保険がおりて、ステキなお家を建てた人がいるんですが、火災保険って儲けることができるんですか?
この記事ではこんな疑問にお答えします。
結論としては、
ただし、結果論として「儲かった」と思えるケースも・・・
「ボロ家が火事で燃えて、建物再建したらすごくきれいな家になった」とよく聞きますが、これにも理由があります。
この記事では、火災保険で儲けられる理由と、いい家が建つ理由、さらには「損をする人」との違いをわかりやすく解説していきます。
- 火災保険の仕組み
- 火災保険で儲かる理由
- 火災保険で得する人・損する人
この記事を書いている人 -WRITER-

りん:FP(元税理士事務所勤務)
税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやすく説明しています。その他、アラフォーからチャレンジしているブログ運営や、ペットについても発信しています。
スポンサーリンク
【まずは基本をチェック!】火災保険の保険料と保険金について

まずは火災「保険料」の決め方と、いざという時に実際に下りる「保険金」について見ていきましょう。
火災保険料の決め方
火災保険料は、まずは家や家財の「保険価額」を算出し、その「保険価額」から「保険金額」を設定、そしてその「保険金額」に対する火災保険料を算出します。
それでは、それぞれの用語の意味を見ていきましょう。
保険価額
保険価額は、保険対象物の建物や家財の価値をいいます。
保険価額には、「新価」(再調達価格)と「時価」の2種類あり、保険金額を決める際にどちらかを選択します。
新価(再調達価格)
新価は建物が全焼してしまった場合、同程度の建物を建てることができるよう設定された金額です。

時価
時価の具体的な算出方法は、新価(再調達価格)から「経過年数による価値減と使用されて消耗した分」を引いた金額になります。
経理の減価償却の計算と同じですね。
つまり、保険価額を時価設定していると、建物が全焼してしまった場合、全焼してしまった建物と同等の建物を建築する時は、支払われる保険金額が少ないので、自腹をきる必要が出てきます。

自腹をきりたくなければ、全焼する前の建物よりも劣った建物を建築しなければなりません。
保険金額
保険金額は、火災保険契約の際に設定する契約金額です。
保険金額は「保険価額」を元に算定されます。
保険金額は、実際に保険金が支払われる事故が起きた場合に支払われる保険金の限度額になります。(※個人用火災総合保険の場合、復旧に付随して発生する費用も含めて保険金額の2倍が限度額になります。)
新価と時価の保険価額のうち、保険金額に設定されるのは、「新価」が主流になっています。
建物が焼失したら、「次は規模を小さく建てたい」とか「次は賃貸でいい」という希望があれば、「時価」を設定するのもアリですが、時価は保険料が安くなるというメリットがある一方、少ない保険金しかでないという面で、デメリットが多くなります。
たとえば、台風被害で屋根の修理をした場合も出る保険金が少ないので、自腹を切らないと修理できなくなります。
このメリット・デメリットを十分説明を受けた上で、保険金額を設定して下さい。
保険金額から得られる補償の具体例
今までの話を具体例を元に再確認してみましょう。
前提条件は以下のとおりとします。
- 25年前に2500万円で新築
- 現在同等程度の建物を建てるのに必要な金額3000万円
- 現在の時価1500万円
新価(再調達価格)で契約した場合
保険契約時の保険金額は3000万円になります。
万が一、火災が発生し全焼した場合におりる保険金は3000万円になります。
つまり、全焼しても、前の建物と同等程度の建物を再建できる仕組みになっています。
時価で契約した場合
保険契約時の保険金額は1500万円になり、新価で契約したときよりも支払う保険料は少なくなります。
ただし、万が一、火災が発生し全焼した場合におりる保険金は1500万円になり、全焼した場合、前の建物と同等程度の建物を再建するには1500万円自分で支出するか、鉄筋を木造にするなどの工夫をする必要があります。
保険金額の決め方
火災(台風被害も含む)があった場合、保険金をどのくらいもらえるかは契約時に設定する「保険金額」によります。(家財も同じ扱いなのでここでは建物について見ていきます。)
保険金額の設定には、次の3つの方法があります。
- 全部保険
- 一部保険
- 超過保険
保険金額を時価にした場合は、計算式がちょっと複雑になるので、ここでは、保険金額を新価で設定した場合を見ていきたいと思います。
全部保険(「新価=保険金額」の場合)
全部保険は、新価と保険金額を同一に設定しているケースを言います。
これによると、損害額に応じた保険金が支払われるので、十分な補償を受けることができます。
保険の主流はこの「新価での全部保険」です。
ほとんどの方が入っているケースだと思います。
一部保険(「新価>保険金額」の場合)
一部保険は、新価よりも保険金額を低く設定しているケースを言います。
一部保険にすれば、保険料が安くなりますが、損害額の一部しか支払われず、十分な補償を受けることができません。
超過保険(「新価<保険金額」の場合)
超過保険は、新価よりも保険金額を高く設定しているケースを言います。
超過保険は、損害額に応じた保険金が支払われるので、十分な補償を受けることができます。
ただし、「新価」が限度額なので、例え、超過保険をかけていても新価を超える補償は受けられません。
つまり保険料は「新価」を超える金額を払っているが、補償は「新価まで」ということなので、補償以上の保険料を払ってしまっているケースですね。
火災保険で儲かる人・損する人

それでは、実際に火災保険で儲かる人を見ていましょう。
火災保険で儲かる人

火災保険は、「保険金額」を限度として、実際の損害額までしか補償されないので、実は「儲かる人」はいません。
が、儲かったように見える人はいます。
そこでこの記事では、「儲かった」と思える(錯覚する)人の具体例を見ていきたいと思います。
儲かったと感じる例①
築年数の古い家が全焼し、保険金で全焼前と同程度の建物を新築した人
家が全焼すると、全焼した家と同程度の家が建つ金額の保険金がおります。
ここでいう「同程度」とは、新築時と同程度です。
つまり、全焼する前の家と新築する家のランクは同じになります。
そして、決定的に違うのは、全焼する前の家は「古い」のに対し、新築した家は「新しい」ということ。
この事実が、「火災保険で儲けた!」と感じる(錯覚する)ことになります。
よく、「焼け太り」と聞きますが、実際に火災保険金で儲けているのではなく、新しい家が建って「儲けた」と錯覚しているだけということになります。
儲かったと感じる例②
保険金で全焼前よりも低い程度の建物を新築した人
例えば、鉄筋コンクリートの3階建ての家が全焼したとしましょう。
家の再建にあたり、例えば、独立して夫婦2人だけになったので、「木造2階建てにしよう」とした場合は火災保険で儲けることはできます。
「新価」で契約していれば、火災保険は、この場合、焼失前の家と同程度(つまり鉄筋コンクリートの3階建ての家)の保険金がおります。
一方で、建てた家は、木造2階建てなので、建築費は全然安くなります。
この差額分、火災保険金は余りますが、この余った火災保険金は返す必要がなく、好きに使ってOKなお金になり、「儲かった」と感じることもあると思います。
儲かったと感じる例③
家を再建しなかった人
家の再建にあたり、「持ち家はやめて賃貸にしよう」とした場合も火災保険で儲けることはできます。
実は、火災保険は、保険金が余っても返却する必要はありません。
「新価」で契約していれば、火災で被った被害分、保険金が出ますが、その火災保険金の使い道は自由なんです。
なので、同程度の家を建てる必要がない方は、火災保険金が余り、結果「儲かった」ことになります。
保険料を払っている期間が長くても短くても、もらえる保険金は同じなので、築年数が浅い建物ほど、お得感はあることになります。
とは言え、火災になると大事な思い出の品も無くなってしまうので、うれしくはないですよね。
儲かったと感じる例④
保険金を請求したが修理をしなかった人
火災保険金は、契約によりますが、台風などの被害も請求することができます。
きちんとした申告をすれば、火災保険金は必ずもらえますが、修理をしなければ、そのもらえた保険金は丸々自分の手元に残ります。
そのお金で旅行しても貯蓄してもOKです。
ただし、後日、また災害の被害にあった際は、保険金をもらっても修理しなかった場所については、当然、保険金は出ませんので注意して下さい。
儲かったと感じる例⑤
臨時費用保険金が出た人
臨時費用保険金とは、災害や事故などで損害を受けた際、臨時に出費する費用として自由に使うことができる保険金です。
これは、建物や家財の実損額の10%~30%ほど支給されます。
例えば、火事で全焼してしまった場合、建て替え費用だけでなく、引越し費用や家財を一時的にトランクルームへ保管するなどの費用が必要になるかもしれません。
そういった臨時に出費する費用として自由に使えるお金です。
この臨時費用保険金も使わなくても返却する必要はないので、残れば「儲かった」と思うかもしれませんね。
この臨時費用保険金は、火災保険とセットになっていない場合もありますので、注意して下さい。
火災保険で損する人

火災保険で儲けられる人は、「そもそも必要な修理や再建をしない」という選択により成り立っているため、感覚的に「儲かった」と思うかもしれませんが、実質的には、「儲けている」という人は存在しないことになります。
その逆で、「損する人」は実質的にいます。
この記事では、損している人を具体的に挙げてみました。
「自分は損している人になっていないか」確認してみて下さい。
損している例①
保険金を請求していない人
火災保険金は、火災だけでなく台風被害などでも請求することができます。
例えば、風災で屋根が壊れたとか、塀が壊れたという場合、みなさんどうされていますか?
私は、FP資格を取るまで無知だったせいで、お恥ずかしながら、自腹で直していました。
でも、これ、保険で直ります。そして、保険契約書を確認すると意外に保険で直せるものがあるんです。
火災保険は、保険料の支払いという「義務」は果たしていますが、保険金請求の「権利」を行使している人は意外に少ないのが現状です。
こういった方は、明らかに「損している人」なので、この機会に火災保険契約書を手に取り、請求漏れがないか確認してみて下さい。
火災保険請求にも時効があります。(通常3年です。ただし、契約により違う可能性もありますので、契約書で必ず確認して下さい。)
でも、火災保険の請求って簡単にできるの?
火災保険の請求は簡単にできます。
請求方法については、「【自分で簡単に申請できる】火災保険の請求方法|知っておきたいコツを伝授 」で詳しく解説しています。
万が一、「自分で請求できるか不安」とか、「請求できるかよくわからない」という事であれば、火災保険申請サポート会社がおすすめです。
ただし、火災保険申請サポート会社にもデメリットがありますので、そのデメリットを確認の上、検討してみて下さい。
>>【怪しい・・・】火災保険申請代行サポートは違法じゃないの?|悪徳業者の見分け方
損している例②
一部保険で契約している人
一部保険で契約している人は、被害にあっても、実損金額の全額は出ません。
もちろん、「保険金は少額でいい」という方もいらっしゃるとは思いますが、損失分をキチンともらいたいちいう方は、全部保険に加入することをおすすめします。
一部保険は保険料が安いですが、損失をすべてカバーできない分、「損」しています。
「火事で全焼」なんてケースは確率は低いですが、先程も例を挙げたとおり、意外に火災保険のお世話になることはあります。
その際に、全額補償してもらうには「全部保険」が必須です。
損している例③
超過保険で契約している人
保険価額よりも多く保険をかけている人も「損」をしています。
なぜなら、保険金は保険価額から算定された保険金額を上限として支払われるので、いくら火災保険料を払っても、もらえる金額は同じだからです。
それじゃ、「保険料払い損」ですね。でもそんな人いますか?
実はいるんです。
通常、保険会社では超過保険になるような契約はしません。
ただ、以下のケースでは超過保険になります。
- 故意的に2ケ所の保険会社と契約した場合
- すでに保険会社と契約しているのを忘れて、もう1社の保険会社と契約した場合
もちろん、火災保険は複数社と契約することも可能です。
ただし、その場合は、「他の保険会社とも契約している」と告知する義務があります。
また、ローンを組んだ際などに、火災保険を契約したにも関わらず、新居に住む際にも火災保険契約をしたことを忘れて、再度、火災保険を契約してしまう人もいるそうです。
その場合は、ローンを組んだ際の契約と新居に住んだ際の契約、2つとも有効ですが、実際に被害にあったときは、実損被害分だけしか保険金はおりません。
1社と契約した場合と複数社と契約した場合でも同額の保険金しか支払われないので注意して下さい。
超過保険に気がついたら、全部保険に変更しましょう。
でも、保険金請求時に2社それぞれに申請すれば、2社とも保険金がもらえるので、結果、保険金が2倍になるんじゃないですか?
保険金請求時にも「他の保険会社とも契約している」と告知する義務があります。
告知義務をせず、多くの保険金を受け取った場合は、詐欺罪になる可能性がありますので注意して下さい。
損している例④
保険金額を「時価」で契約している人
保険金額を時価で設定している方は、確かに支払う保険料は少なくなります。
ただし、万が一の際に受け取れる保険金は、その時の建物評価額になってしまいます。
1年更新の火災保険であれば、保険金額を時価にした契約をしても、損害がその契約年にでれば同じ時価評価した保険金がもらえるので、トントンになります。
ただし、新価のように全額補償されないという意味では、一部保険になってしまいます。
一部保険なので、修理をする際も、建物を立て直す際も、自腹をきるか、グレードを下げる必要がでてきてしまい、結果「損」する人になります。
また、たとえば5年契約をしてしまうと、「一部保険」にもなり「超過保険」にもなりうります。
例えば、今、再調達価格3000万円の建物を時価の1500万円で5年契約したとします。
その5年契約の5年目で全焼してしまったとします。
そして、5年目の建物の時価が1000万円だったとするとどうでしょうか。
1500万円分の保険料を払っていたのに、1000万円分の保険金しかもらえないということになります。
これが時価の「超過保険」です。
しかも再建に必要な3000万円には程遠いので、「一部保険」になっていると言っても過言ではありません。(ここでは、簡単に書きましたが、時価契約の保険金の支払いは複雑になっていますので、契約時に必ず確認して下さい。)
時価契約は保険料が安く「得」をしているように見えますが、実は「損」になる可能性が大きいので、契約時によく相談して決めてください。
まとめ:火災保険で儲けることは難しい|安心のためにキチンとした保険に入ろう

火災保険は「実損払い」なので、基本的に儲けることはできません。
ただ、必要がある修理をしなかったり、再建する建物のグレードを落としたり、そもそも再建自体しなければ、「儲かった」と感じることもあるでしょう。
それでも、全損すれば大事な思い出はなくなっている可能性も多く、いくらお金をもらっても、素直に喜べないですよね。
「全焼したら儲かった!」という人はほとんどが、なんの関係もない人のうわさであることが多いです。
私もよく、「○○さんは火事にあったらいい家を建てた。うらやましいわ~。」なんて世間話を聞きますが、実際の当事者になったらそんな気持ちにもなれないと思います。
当事者として思うことは1つ。
火災保険に入っていて良かった・・・。
この1点だと思います。
保険商品はいざという時にしかありがたみがわかりませんが、そのいざという時に役立つ保険の入り方を是非考えてみて下さい。
時価契約や、一部保険・超過保険は「損」になります。
時価契約や一部保険が「得」になるときは、何の被害も合わずに一生を終えられたときでしょうか。
火災保険では、台風などの被害にも使えます。
皆さんが利用していないだけで、意外と使える保険です。
ぜひ、損をしない入り方をして、さらには、損をしないよう少しの被害でも火災保険申請して下さい。
特に、家財保険は申請できるものも申請せず「損」をしている方が多いです。(詳しくは「【家財保険】わざと壊した場合も申請できる?|家財保険の裏ワザも紹介 」で記載しています。)
火災保険は、何度申請しても、保険料が上がることはありません。
>>火災保険を一度使うと保険料が上がる?|デメリットも詳しく解説!
実は、2022年10月より火災保険が大幅に値上がりします。
また、保険期間も最長10年から5年に短縮されます。
>>【火災保険10年廃止はいつから?】2022年10月火災保険値上げで過去最大の負担増!
この機会にぜひ、火災保険の見直しをしてみて下さい。
火災保険は損害保険会社により補償がさまざまです。
また、火災保険は、同じ内容でも会社によって保険料が全然違います。
ですので、色々な損害会社から見積をとり、比較検討することが必須です。
ただ、火災保険を自分ですべて吟味することは到底できません。
そこで、火災保険一括見積もりの活用をおすすめします。
サイト名をクリックすると公式HPにアクセスすることができます。
| 住宅本舗 |
|||
|---|---|---|---|
| 見積数 | |||
| 公式HP |  |
 |
火災保険見積サイトについては下記で詳しく解説しています。
>>【完全保存版】火災保険一括見積もりのおすすめ3選|メリット・デメリットも解説!
火災保険一括見積もりでは不安な方は、無料保険相談窓口という手もあります。
火災保険の相談には、取扱会社が多数ある、保険見直し本舗がおすすめです。
その他の無料保険相談サービスは以下のとおりです。
|
保険見直しラボ
|
保険見直し本舗
|
保険マンモス
くわしく見る |
保険のトータル
プロフェッショナル |
保険ガーデン
|
みんなの生命保険
くわしく見るアドバイザー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗相談 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 訪問サービス | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| オンライン相談 | ○ | ○(電話相談も可) | - | - | - | - |
| 生命保険 | ○(21社) | ○(24社) | ○(店舗による) | 派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
| 損害保険(火災保険) | ○(11社) | ○(13社) ※ペット保険2社含む |
- | 派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
派遣される FPによる |
| 公式HP | 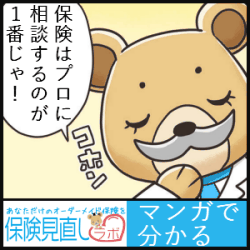 |
 |
 |
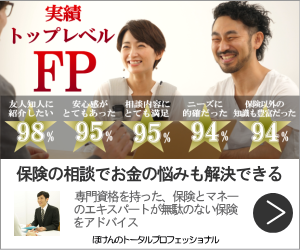 |
 |
無料保険相談窓口では、必要書類を持っていけば、窓口の方がそれを見て、保険を選んでくれるので、こちらで資料を読み解く必要はありません。
火災保険はちょっとした選択でも金額が変わってしまい、実は結構難しい保険です。
保険は、プロのアドバイスを元に選びましょう。
保険の窓口についてはこちらの記事を参照して下さい。
無料で相談にのってくれることに不安を覚える方は、「【無料保険相談のカラクリを暴露!】中立で相談できる理由は? 」で記事にしていますので参考にしてみて下さい。











