
個人事業主が簡単に節税できる裏技ってありますか?
この記事ではこんなお悩みを解決します。
個人事業主やフリーランスの方は、所得が増えると、税金以外に負担が増えるものがあります。
一例を挙げてみましょう。
所得税・住民税・個人事業税・消費税・国民健康保険料・保険負担割合(2割の人が3割になる可能性あり)など
いろんなものに影響するんですね。
個人事業主は社会保障も恵まれていないし、所得が増えると負担もいろいろ増えるので、自分で対策を練らなければなりません。
(個人事業主やフリーランスのデメリットについては「【フリーランスやめとけ】社会保険・保障はデメリットだらけ|後悔しないための解決策あり 」で記事にしています。)
この記事では、簡単で即効性のある裏ワザをわかりやすく解説しています。
すぐに使える裏ワザばかりなので、できるものから実践して下さいね。
- 節税のポイント
- 経費面での節税の裏ワザ
- 所得控除面での節税の裏ワザ
この記事を書いている人 -WRITER-

節税のポイントと節税の大前提

まずは、この記事の大前提として、「脱税」方法はご紹介していません。
もし、「税務署を出し抜く裏ワザ」を期待した方は、そっと画面を閉じてください。
この記事では、簡単にできる「正当な節税」の方法をわかりやすくご紹介します。
節税のポイント
一言で「節税」と言っても、節税できる場所が大きく分けると2つあります。
それは、経費面と所得控除面です。
あれ?
両方とも「売上から差し引ける」って意味では同じですよね?
分ける必要ってありますか?
実はあるんです。
この2つの大きな違いは「費用計上できるかできないかです。」
下の計算式を見てください。

節税するには「課税所得」を少なくする必要があります。
そしてこの「課税所得」を少なくするには、支出を増やすしかありません。(売上は故意的には減らせないのでここでは論点にあげません。)
その支出は「経費」と「所得控除」の2種類あります。
ここを減らして、節税していきますが、この内、「経費」しか費用計上できません。
「所得控除」も支出なのに費用計上できないんですか?
ここはちょっとわかりづらいので、生命保険料を例に具体的にお話ししていきますね。
生命保険を支払った際の仕訳は法人の場合と個人の場合では違います。
法人の場合:保険料 ○○円/現預金○○円
個人の場合:事業主貸○○円/現預金○○円
※すべて費用計上できる生命保険と仮定します。
あれ?生命保険料って「保険料」で計上できないんですか?
生命保険料は個人では、「保険料」になりません。
サラリーマンの方も、生命保険料を費用計上せず、「所得控除」で全額ではなく、決まった計算式に当てはめて出した金額を「生命保険料控除」という「所得控除」を受けていますよね。
それと同じ扱いなので、一旦、「事業主貸」という「資産」勘定に計上します。
「資産」勘定なので、「費用」にはなりません。
このように、所得控除面の節税方法は、一旦、「事業主貸」という「資産」勘定に計上します。
ここを費用計上して確定申告をすると、事業所得でも費用計上した上に、所得控除でも控除して2重控除になり、予期せぬ脱税行為になりますのでくれぐれも注意して下さい。
節税の大前提
つぎに節税の大前提を2つ上げたいと思います。
- 申告は正しくする
- 申告は青色申告にする
申告は正しくする
当たり前ですが、申告は正しくしましょう。
脱税行為をして、一時、得をしたとしても、それが見つかれば、追徴課税され、大損してしまいます。(追徴課税については「追徴課税・加算税ってなに?税率は?時効は?|住民税・社会保険にも影響 」でくわしく記事にしています。)
脱税行為をすれば、金銭的に損をするばかりでなく、取引先にバレれば信用も失います。

申告は青色申告にする
申告は、特典が盛りだくさんの青色申告にしましょう。
青色申告には、10万控除と55万控除(一定の場合は65万円控除)の2種類ありますが、できれば、55万円控除を選択しましょう。
青色申告については、国税庁のHP「青色申告制度|国税庁」でご確認下さい。
経費計上で節税できる簡単裏ワザ

ここでは、個人事業主が経費計上で節税できる簡単裏ワザをご紹介します。
- 日常の生活で経費化できるものを見直す
- 少額減価償却資産の特例を使う
- 中小倒産防止(経営セーフティー共済)に加入する
- 青色申告で親族のお給料を費用計上する
それでは1つ1つ見ていきましょう。
日常の生活で経費化できるものを見直す
日常の生活で費用化(経費化)できるものを見直して下さい。
その際、注意したいのが、全額費用計上できるものと家事案分が必要なものがあるということです。
全額費用計上できるもの(例)
仕事で乗った電車代・仕事で使ったタクシー代・仕事で使った高速代・書籍代・打合せ食事代・接待した場合の飲食代 など
誰が見ても明らかに「事業用のみ」に使った費用は経費化できます。
全額費用計上できないもの(例)
家事案分が必要なもの
自動車の減価償却費・ガソリン代・住居の家賃・水道光熱費・電話(携帯代) など
事業とプライベートの両方で使っているものは家事案分する必要があります。
合理的な基準とは、床面積や使用時間で計算される基準をいいます。
この家事案分は、税務調査でも問題になるところなので、キチンとした根拠の元、割合を決めましょう。
税理士さんに相談することをおすすめします。
少額減価償却資産の特例を使う
青色申告の特典の1つです。
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満なら、本来であれば数年に分けて計上している減価償却費を、取得した年で一括で費用計上できる特例です。
この特例を使えば、取得した事業年度の必要経費を増やすことができます。
税込処理をしている場合は、税込の金額で30万円未満です。
税抜処理をしている場合は、税抜の金額で30万円未満です。
(消費税の税込・税抜処理については「【消費税仕訳】税込経理・税抜経理どちらがお得?メリット・デメリットも解説 」で詳しく記事にしています。)
中小倒産防止(経営セーフティー共済)に加入する
中小倒産防止(経営セーフティー共済)とは、取引先が倒産した場合に、経営難や連鎖倒産に陥ることを防ぐ制度です。
掛金は月5,000円から掛けることができ、すべて費用計上できます。
保険料・損害保険料・支払保険料などの科目を使って費用計上して下さいね。
<<経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構)公式HPはこちらから
青色申告で親族のお給料を費用計上する
青色申告で確定申告すれば、親族のお給料を費用計上できます。
これを「青色事業専従者給与」と言います。
認められる条件は以下のとおりです。
- 青色申告を行っている者と生計を一にする配偶者やその他の親族
- 申告を行う年の12月31日に15歳以上
- 年間6か月を超える期間(一定の場合は、事業に従事できる期間のうち2分の1を超える期間)、青色申告者の営んでいる事業に従事している
- 事前に「青色専従者給与に関する届出書」を提出している
もちろん、自分の事業を手伝ってもらっている実態がなければ申請できませんので注意して下さいね。
「経理を担当してもらってる」「発送業務を担当してもらってる」などがあれば是非、申請しましょう。
ここで注意したいのが、青色事業専従者給与を選択すると、金額のいかんにかかわらず、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。
なので、青色専従者給与を選択した方がいいのか、配偶者控除を選択した方がいいのか、有利判定して選択しましょう。
また、税務調査があると「実態とお給料が適切か?」が問題になります。
相場と照らし合わせ、説明がつくお給料を設定しましょう。
悪い例として、以前、奥様のお給料の支払い理由として、「主婦としてのアドバイスを受けている」というものがありました。
これは、その方がコンサルタントやアドバイザーとして、「主婦としてのアドバイス」でお金を稼げるだけのものがないと、ほとんどがアウトになる事例ですのでくれぐれも注意して下さい。
所得控除で節税できる簡単裏ワザ

ここでは、個人事業主が所得控除で節税できる簡単裏ワザをご紹介します。
- 医療費控除を受ける
- 小規模企業共済に加入する
- 生命保険に入る
- iDeCo(イデコ)に加入する
前章でも述べたように、所得控除で節税できる裏ワザは、費用計上できません。
事業用の通帳から引き落としや振込をした場合で、どうしても仕訳しなければならないときは、下記の様に仕訳して下さい。(国民健康保険料や所得税・住民税の納付も同じ仕訳になります。)
事業主貸○○○円/現預金○○○円
それでは1つ1つ見ていきましょう。
医療費控除
医療費控除は10万以上の医療費がないと控除できないとあきらめていませんか?
医療費が10万円以下でも「医療費控除」が受けられる場合があります。
医療費控除には原則と特例があります。
医療費控除の原則
医療費控除の原則は総所得金額等が200万円以上の場合と200万円未満の場合と2通りあります。
①総所得金額等が200万円以上の場合
その年に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-10万円
総所得金額等とは、簡単に言うと、すべての所得の合計額です。
この総所得金額等が200万円以上ある人は、10万円を超えた金額が医療費控除の金額になります。
②総所得金額等が200万円未満の場合
その年に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-総所得金額等の5%
すべての所得の合計額が100万円の場合は、100万円×5%=5万円を超えた金額が医療費控除の金額になります。
所得の低い人は、医療費が10万円超えなくても医療費控除が受けられる可能性があるのであきらめないで下さいね。
くわしくは「【医療費控除】いくらからでいくら戻るの?計算方法をわかりやすく解説 」で記事にしています。
医療費控除の特例
もう1つ、医療費が10万以上にいかなくても使える医療費控除の方法があるます。
それは、「セルフメディケーション税制」です。
この特例は2021年まで使える特例になっていますが、所得の多い人でも適用できる税制なのでぜひ検討してみて下さい。
セルフメディケーション税制については、「【10万以下でも医療費控除】セルフメディケーション税制をわかりやすく簡単に解説 」で詳しく説明しています。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済とは、事業主の退職金を積み立てる制度で、65歳以上になった場合や事業を廃止した場合に、一時金もしくは年金として給付を受けられる制度です。
掛金は毎月1,000円~70,000円から選択できます。
この小規模企業共済については、「加入必須」と言われるくらいお得なので、是非検討してみて下さい。
この小規模企業共済がすごいところの1つに、「加入時期」があります。
なんと、12月に加入しても、加入年なら何か月前までさかのぼって掛金を支払うことができるんです。
例えば、2021年の12月に所得が多いことに気が付いて、節税のために加入しようとした場合、通常なら2021年12月からの加入になりますが、この小規模企業共済は2021年1月から加入をさかのぼれます。
この方法を取れば、1月分~70,000円掛金をかけたことにして、12月末日までに70,000円×12ヶ月=840,000円払えば、その840,000円全額、小規模企業共済(所得控除)を受けられます。
<<小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構)公式HPはこちらから
生命保険
個人事業主で入る生命保険は経費にはなりませんが、サラリーマンと同様、生命保険控除の対象になります。
個人事業主はサラリーマンに比べて、社会保障が充実していません。
その不足分を保険でカバーして、合わせて所得控除も受けましょう。
(個人事業主の社会保障の脆弱性については、「【フリーランスやめとけ】社会保険・保障はデメリットだらけ|後悔しないための解決策あり 」で記事にしています。)
保険って難しくて良くわからいなぁ・・・。
今はFPに無料で相談できる窓口があります。
ここではおすすめの保険相談窓口をピックアップしました。
|
マネードクター
|
保険チャンネル
|
保険見直し本舗
|
保険見直しラボ
|
保険マンモス
くわしく見る |
保険ガーデン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗相談 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 訪問サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○(電話相談も可) | ○ | - | - |
| 生命保険 | ○(22社) | ○(14社) | ○(24社) | ○(21社) | ○(店舗による) | 派遣される FPによる |
| 損害保険 | ○(10社) | ○(14社) ※ペット保険2社含む |
○(13社) ※ペット保険2社含む |
○(11社) | - | 派遣される FPによる |
| 公式HP | |
 |
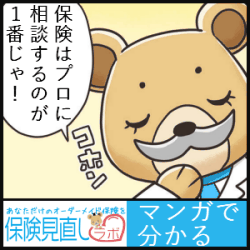 |
 |
 |
こちらからすぐに相談を申し込めるので、気になった保険窓口相談があったら申し込んでみて下さいね。
保険の窓口についてはこちらの記事を参照して下さい。
マネードクターでは、専門性の高いFPが多く在籍しています。
<公式>マネードクター
その他の無料保険窓口にもそれぞれ特徴があります。
です。
相談相手はできる限り自分と同じ境遇、または話しやすい人がいいですよね。
そんなこだわりがある方は、保険チャンネルがおすすめです。 ![]()
iDeCo(イデコ)
年金額を増やしたいなら、iDeCo(イデコ)も1つの手段です。
掛金額が全額所得控除の対象です。
ただし、iDeCo(イデコ)は一方で「課税の繰り延べ」と言われているように、受取時に非課税枠を超えた部分は課税の対象になります。
また、次の方にはデメリットが多いのであまりおすすめしません。
- 納める税金が少ない方
- 将来、年金や退職金が多くもらえる方
所得が少なかったり、住宅ローン控除などの控除を受けて、納める税金が少ない人は、節税効果がありません。
また、将来、年金や退職金が多くもらえる方は、非課税枠がもうないか少ないので、iDeCo(イデコ)の恩恵が少なくなります。
会社員であれば厚生年金だけでも年金の非課税枠は超えるので、iDeCo(イデコ)の年金受取額は実質課税されます。
退職金の非課税枠が残っていれば一時金でもらった方が節税効果が望めます。(ただし一時金でもらう金額は年金方式でもうら金額よりも少なくなる場合があるので、総合的に判断しましょう。)
iDeCo(イデコ)は元本保証ではありません。また、管理手数料もかかります。
ただし、将来、年金形式でお金がもらえるのは安心材料ではあります。
そういった、メリット・デメリットを十分考慮し、選択して下さい。
(iDeCo(イデコ)については、「【超簡単解説】iDeCo(イデコ)やめとけは本当?|デメリットは? 」で詳しく説明しています。)
おすすめのiDeCo取扱金融機関は以下のとおりです。
|
マネックス証券
くわしく見る |
松井証券
|
|
|---|---|---|
| 運営管理手数料 | 無料 | 無料 |
| 取扱商品数 | 27 | 31 |
| サポート体制 | 平日9:00~20:00 土曜9:00~17:00 |
平日8:30~17:00 |
| 公式HP |  |
|
資料請求は無料ですので、iDeCoの仕組みやメリット・デメリットを検討してみるのも1つの手です。
まとめ:個人事業主の節税方法を知り、最大限活用しよう!

節税をするにあたって、大事なことは「脱税」にならないことでした。
- 申告は正しくする
- 申告は青色申告にする
脱税になってしまえば、脱税になった時点では「得」をしますが、それがバレたときは「得」以上の「損」を被ることになります。
その「損」の中には、国民健康保険料の増加や税金などの追徴課税の他にも、反面調査があった場合は取引先への信頼性も失われます。
そうならないためにもくれぐれも合法的な節税対策を心がけてください。
どこまでが「合法」でどこからが「違法」なのかわからないのですが・・・。
そんなときは税理士さんに確認して下さい。
税理士費用が高いと主張する方がいますが、売上や事業規模、仕訳量などで、思ったよりも費用がかからない場合が多いです。
そもそも税理士費用は経費になり、「節税」という意味でも、その経費を払った以上のメリットがあります。
今回ご紹介したものは顧問税理士がいれば、当たり前に提案してもらえます。
今この記事を読んでいる方は、ネット検索の方がほとんどだと思いますが、税理士を雇えば、このネット検索の時間も自分の仕事の時間に充てることもできます。
もしいい税理士さんを探したいということであれば、無料で探せるサービスがありますので活用してみて下さいね。
紹介される税理士は全て面談により厳しい審査(経験・知識・人柄)に合格済み
さらにHPが充実しているので一見の価値あり!(不安も解消されます)
<<詳しくは税理士紹介エージェント公式HPへ
登録税理士全国5,800名以上で、上場企業が運営している紹介会社なので安心!
>>詳しくは税理士ドットコム公式HPへ
税理士も税理士を探している人も満足度が高い紹介会社
今なら1万円の商品券がもらえる!
<<詳しくは税理士紹介ラボ公式HPへ
所属税理士には独自の登録審査がある紹介会社
<<詳しくは税理士紹介ネットワーク公式HPへ
2~3か所に登録して税理士事務所を選ぶのがおすすめです。
口コミなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
また、税理士費用を極力抑えたいという方は、自分で会計データを入力(自計化)すれば、税理士費用は少なくなります。
- freee
<< 会計ソフトfreee公式HPへはこちらから
👉『freeeの特徴・料金・口コミ』で詳しく説明しています。 - マネーフォワードクラウド
<< マネーフォワードクラウド公式HPへはこちらから
👉『マネーフォワードクラウドの特徴・料金・口コミ』で詳しく説明しています。 - 弥生会計
【法人用】
<< 弥生会計 オンライン公式HPへはこちらから
👉『弥生会計オンラインの特徴・料金・口コミ』で詳しく説明しています。
【個人用】
<< やよいの青色/白色申告オンライン公式HPへはこちらから
👉『やよいの青色/白色申告オンラインの特徴・料金・口コミ』で詳しく説明しています。
【クラウド型会計ソフト徹底比較】個人事業主におすすめ|3選 - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】
それでは、節税の裏ワザをまとめてみましょう!
- 日常の生活で経費化できるものを見直す
- 少額減価償却資産の特例を使う
- 中小倒産防止(経営セーフティー共済)に加入する
- 青色申告で親族のお給料を費用計上する
- 医療費控除を受ける
- 小規模企業共済に加入する
- 生命保険に入る
- iDeCo(イデコ)に加入する
その日から簡単にできるものや、届出が必要なもの、そして、FPに相談した方がいいもの、税理士に相談した方がいいものもあります。
この裏ワザを完璧に使いこなし、最大限の節税効果を得るには、相談できるものは最大限活用してみてましょう。
【関連記事】生命保険料控除にもなる「個人年金」について年代別にわかりやすく解説しています。
【関連記事】時間がないときの最終手段の申告方法を記載しています。










