
最近、相続問題はお金持ちだけでなく、一般家庭にも多いと聞きますが、うちは大丈夫か心配です。
この記事ではこんなお悩みを解決します。
先に結論!
その中でも、特に相続で揉める家族にはある特徴があります。
ただし、対策を講じておけば、ある程度は回避は可能です。
以前は相続問題はお金持ちの問題でしたが、昨今では、ネットなどで情報があふれ、お金がない家庭でも、少なからず相続問題が起こります。
裁判所の「司法統計」によると、家庭裁判所の相続に関する調停の数は、令和2年度はコロナの影響か若干少なめですが、それでもおおよそ1万1,000件です。

この表で注目すべきは、もう1つ。
解決には、多くは半年から2年ほどかかっています。
ただし、「解決」と言っても、相続で揉めてこじれてしまった関係は一生続くことが多いことも被相続人は頭に入れておくべきでしょう。
このことからも、自分の死後も家族が良好な関係を保てるよう、キチンと対策しておく必要がありますね。
でも、相続問題はお金持ちの話ですよね?
いえいえ、実はお金持ちよりも、相続財産がない(少ない)人の方がトラブルが多いんです。


右統計を円ブラフにしました。
これによると、令和2年度に家庭裁判所の調停で解決した事例は、1,000万円以下が35%、5,000万円以下が最も多く43%と、5,000万円以下の財産で揉めているのは全体のおよそ78%、8割近くにも及びます。
相続財産が多い人が揉めていないで、少ない人が揉めるのはどうしてですか?
理由は2つあります。
それは、
- 相続財産が多い人は生前にキチンと「対策」をしているから
- 相続財産が少ない人は、現金など簡単に分けられる財産が少ないから
が主な原因です。
加えて、相続で揉める原因は「お金(財産)」というよりも「人(家族)との関係性」の場合が多いと、税理士事務所勤務時にお客様と接するたびに感じていました。
そこで、本記事では、税理士事務所勤務時に経験した相続問題も踏まえ、まずは「相続で揉める家族の特徴」をあげ、その根拠と解決策を提示していきます。
★保険の見直し、相続対策の保険相談は下記アプリで簡単にアドバイスがもらえます。
\ 無料で診断! /
- 何回でも利用可
- 住所・氏名・電話番号などの個人情報不要
- 希望があれば相談にものってもらえる
- 相続で揉める家族の特徴と原因
- 相続で揉めない解決策
この記事を書いている人 -WRITER-

相続で揉める家族の特徴10選

相続で揉める原因は「お金」だけではありません。
相続人同士の「不平等感」も相続で揉める原因の1つです。
ひと昔前は、長男が家督を継ぎ、家督を継いだ長男が親の面倒を見て、土地建物や現金などの財産を継ぎました。
次男は自力で財力を付ける必要があり、娘は嫁に行くしか選択肢がなく、「不平等」な世の中でした。
一方、現代では、家督を継ごうが継ぐまいが、親の面倒を見ようが見まいが、「相続人には平等に遺産が分割される」法律になりました。
ただ、この「平等」という言葉、聞こえはいいですが、介護などの面倒を見た相続人からすれば、「不平等」な一面もあります。
現代の法律では、こういった問題を置き去りに、法定相続分を基準に均等に分割することが「平等」と称されるようになってしまいました。
この様に「平等」という理念を掲げた法律により、「不平等」が発生し、相続問題が誰にでも起こりうる問題に発展してしまいました。
相続問題の発生原因は1つだけではなく、以下であげる原因が複数積み重なって起こることがほとんどです。
まずは、「相続で揉める家族の特徴」を見ていきましょう。
- 相続が発生する前から仲が悪い又は連絡を取り合っていない
- 生前に多額の贈与をされた相続人がいる
- 被相続人の介護をした相続人がいる
- 被相続人と同居していた相続人がいる
- 被相続人の財産管理を1人の相続人がしていた
- 土地建物などの換金されにくい資産が多い
- 被相続人が事業をしている
- 想定していない相続人がいる
- 再婚などで人間関係が複雑
- 相続人や相続人の家族にクレーマー気質の人がいる
- 相続人にお金が必要な人がいる

特徴①
相続が発生する前から仲が悪い又は連絡を取り合っていない

相続が発生する前から仲が悪い場合は、必ずと言っていいほど、相続問題が勃発します。
遺言書がなく話し合いで解決しなければならない場合には、基本的には法定相続分に沿って話し合いが進められます。
しかし、仲が悪い相続人どうしでの話し合いでは、それぞれが少しでも、
- 価値があり
- 換金性の高い
相続財産を得ようと画策します。
こういった場合、「他の相続人よりも法定相続分以上の遺産を得よう」とし、それに他の相続人も応対することになり、話し合いがまとまりません。
さらに激化すると、遺産分割協議の場がお互いの誹謗中傷の場になり、精神ばかり消耗してしまいます。
また、音信不通の相続人がいた場合は、その相続人が見つかるまで、遺産分割協議はできず、長期化します。
親や兄弟と絶縁関係でも、音信不通でも、所在不明でも、法定相続人である以上、相続権は存在します。
遺産を相続する為には、「遺産分割協議書」への署名捺印が必要ですが、この書面は「相続人全員の同意」が必要です。
そのため、絶縁関係の相続人にも連絡を取り、話し合いをする必要があります。
ただし、絶縁関係にあった人との話し合いは、壮絶な状況になり得ますので、できれば弁護士に依頼することをおすすめします。
もし、連絡先がわからなかった場合はどうすればいいですか?
その場合は、「不在者財産管理人」を立てましょう。
不在者財産管理人とは 行方不明や連絡先がわからない相続人の代わりに財産を管理する代理人のことです。
利害関係者からの申し立てにより家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことによって、遺産分割を進めることができます。
「相続放棄する!」と言って、出て行った場合は、連絡が取れなくても相続を開始しても大丈夫ですよね?
実は、被相続人が存命中には相続放棄はできません。
つまり、相続放棄は被相続人が死亡してから手続きを行う必要があるので、被相続人が死亡したら、すべての法定相続人に連絡を取る必要があります。
【関連記事】相続放棄の失敗例やメリット・デメリットを詳しく解説
(参考)生前に相続放棄はできない!その理由や生きている間にできる策を紹介|相続弁護士ナビ
特徴②
生前に多額の贈与をされた相続人がいる

生前に被相続人から多額の贈与を受けていた場合(これを「特定受益」といいます)、相続問題に発展することがあります。
例えば、結婚資金や住宅購入資金、事業資金の援助などが、「特定受益」としてあげられます。
また、稀ではありますが、他の相続人が高校までしか行かなかったのに、1人だけ大学まで出してもらえたとか、その逆に、みんな大学まで出してもらえたのに、自分だけ高校までしか出してもらえなかった場合でも相続問題に発展する場合があります。
このように、当時は「ずるいな」とか「いいな」と思っていても言葉には出していなかった感情が、相続の話し合いで不満が爆発し、相続トラブルに発展することも少なくありません。
特徴③
被相続人の介護をした相続人がいる

先程お話ししたとおり、今の法律では、相続人の権利は「平等」です。
被相続人の介護をした相続人も、何もしなかった相続人も、遺産は「平等」に分割されます。
どうでしょう。この「平等」は、介護をした相続人からしたら「不平等」にしか感じ取れませんよね。
この介護をした相続人にとっての「平等」は、自分が介護をした分、多く遺産を相続させてもらうことになります。
ですが、いくら生前の親の面倒や介護をしてきたことを主張しても、他の兄弟が首を縦に振らない限り、法定相続分しかもらえません。
また、例え、これらの功績を認めてもらったとしても、貢献割合で揉めるケースも多々あります。
こういった場合、「親の面倒を見てくれたのは感謝しているが、その分、(生活費や娯楽で)親のお金を使っているだろう」とか、「生活費以上に親のお金を引き出しているんじゃないのか」と、少しでも割合が平等になるよう主張されることも多いです。
もっとひどい場合は、「親はうちに来るといつも愚痴っていた。かわいそうだった。」と面倒も見ない兄弟が言うこともしばしば・・・。
誰だって一緒に住めば愚痴もでます。 それでも一緒に住んで、面倒を見た努力が「0」になる訳ではないのですが、面倒を見なかった人に限って権利を主張してくるものです。
でも、法律は「平等」。
この「平等」への思いの違いが、相続争いの起因になることも多くあります。
ここで私が、以前、勤務していた税理士事務所で経験したお話しを少ししたいと思います。
相談に来られたお客様は、入院していた親の介護のため、毎日病院に通った交通費と日当を要求していました。
ここまで聞くと、「自分の親なのに・・・」と思われるかもしれません。
私も最初はそう思っていました。
でも、その方によくよくお話しを聞くと、面倒を見なかった兄弟があまりにも理不尽な言いがかりを言ってくるので、「どうしても多く遺産をもらわないと気が済まい」とのことでした。
「むなしい」とまでおっしゃっていましたが、法律の「平等」には逆らえません。
ただ、近年は、介護や面倒を見た「寄与分」が認められ、他の相続人よりも多く、遺産を受け取れる法律もできました。
ですが、この法律は、相続人同士の話し合いで、寄与分を認めるか、認めるとしたらどの位の割合を認めるかを話し合わなければならず、結局のところ、ほとんど機能していません。
この様に、普段では、お互いに気を遣える相手でも、相続の話し合いでふとしたきっかけで出た不平不満がどんどん広まり、相続で揉める原因になっています。
特徴④
被相続人と同居していた相続人がいる

被相続人と同居していた相続人がいた場合もトラブルの原因になります。
特に、土地建物しかなかった場合、その土地建物の権利について主張される場合もあります。(詳しくは「特徴⑥」で説明しています。)
特徴⑤
被相続人の財産管理を1人の相続人がしていた

被相続人の財産管理を1人でしていた場合、「使い込み」で疑われる場合が非常に多いです。
どんぶり勘定をしていた場合や、通帳から1度に多くの現金を引き出していた場合は、あらぬ疑いがかけられる可能性も。
対策としては、
- 被相続人専用の家計簿をつける
- 通帳から引き出した場合はその理由を通帳にメモしておく
- 領収書をすべて取っておく
などがありますが、そもそも相続で揉めているときは、これらの対策を練っても、トラブルは起こります。
できれば、相続人2人以上で、被相続人の財産管理をすることをおすすめします。
特徴⑥
土地建物などの換金されにくい資産が多い

相続財産に土地建物・株券などの換金性がない資産がほとんどの場合も相続で揉める原因になります。
特に相続人が住んでいる土地建物が相続財産に含まれていた場合は、その分割方法で揉めてしまいます。
土地建物も遺言書がない限り平等に分ける必要があります。
また、例え、「土地建物を同居して介護をしてくれた長男に全て遺贈する」という遺言書があったしても他の相続人には「遺留分侵害額の請求」する権利があります。
「遺留分侵害額の請求」とは、不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求することです。「遺留分」は法定相続分の1/2(配偶者であれば法定相続分1/2の1/2で1/4に値する額になります。)
つまり、遺言書に「愛人に全財産を遺贈する」と記載があっても、妻は、本来の法定相続分1/2の1/2分(全財産の1/4分)の財産を愛人に請求できるということですね。
その他、子が2人いれば、子の法定相続分1/4の1/2で、それぞれの子が全財産の1/8づつ愛人に請求することができます。
「遺留分の侵害額請求」はもちろん兄弟間でも行うことができます。
ですので、先程の例えのように、「土地建物はすべて長男に」という遺言があっても、他の兄弟に最低でも遺留分の現金が残っていないと、「遺留分の侵害額請求」がされれば、土地建物を売って、兄弟に遺留分を支払う必要が出てきてしまいます。
このように、相続人が同居し、相続財産が土地建物しかない場合は、下記対策をしていないと、相続後同居していた相続人が今の場所に住めなくなることもありますので注意が必要です。
特徴⑦
被相続人が事業をしている

税理士事務所でよく経験した相続問題はこの事業継承の問題が非常に多くありました。
飲食店や小売店、または製造業など、親の会社の事業を継ぐことも多いと思います。
生前に、自身の事業の株を、継がせたい、または、継いでくれた子に贈与しておくのも手ですがこれも「特定受益だ」と相続人に主張される可能性もあります。
もし、相続で分けられる財産が会社しかない場合は、他の相続人に相続財産を渡す為に、現金を用意する必要があります。
最悪、事業をやめて株の清算と土地建物の売却という、なんとも悲しい結果にもなりかねません。
継がせようと思っている相続人に事業を継がせたい思いはわかりますが、法律では「平等」です。
なんの対策もしていないと、事業の権利は平等に分割しなければなりません。
後継者につつがなく事業を継がせるために、元気の内に税理士さんや弁護士さんに相談しておきましょう。
特徴⑧
想定していない相続人がいる

相続人には想定していない相続人がいることもありますが、そういった相続人も被相続人にしてみれば、想定済みだと思います。
具体的に例を1つあげると、認知をした子供が「想定していない相続人」でしょうか。
また、家族の知らないところで養子縁組をしていれば、相続人にとっては「想定していない相続人」になるでしょう。
再婚の場合は、子供たちが知らないだけで前妻との間に子供もいるかもしれません。
これらの想定していない相続人も平等に財産を受け取る権利があります。
想定していない相続人が現れると、相続人は心の準備ができていない分、平常心でいられず、先ずは拒否反応から入ります。
この拒否反応により、冷静さはなくなり相続トラブルがますます激化していきます。
【関連記事】前妻の子に相続させない方法は?連絡しなくてもOK?|再婚で起こる遺産相続問題を考える
特徴⑨
再婚や養子縁組などで人間関係が複雑

子連れで再婚した場合も注意が必要です。
例えば、母親が「再婚」で前夫との間の子供と現夫との間に子供がいたとします。
現夫が他界した場合は、前夫との間の子供には相続権はありません。
例え、前夫との子供が小さい時からずーっと一緒に現夫と暮らしていても、老後の面倒を見たとしても、前夫との子供には相続権はありません。
現夫がもし妻の連れ子にも財産を分けてあげたいと思っているなら、キチンとした対策をしないと、例え、子供同士が仲が良くても相続トラブルが発生する可能性があります。
妻の連れ子に自分との間の子と同程度の相続財産を分けたいのであれば、養子縁組する必要があります。
ですが、養子縁組した後、仲が悪くなることもあります。
血の通った親子でも仲が悪くなることがあるので、しょうがないですね。
仲が悪くなったからと言って、簡単に養子縁組は解消できないので、慎重な判断が必要になります。
【関連記事】再婚相手の連れ子への相続はどうなる?|相続させたい場合の対策もあり!
【関連記事】【嫁・婿への相続】マスオさんが波平さんの遺産を相続するには?
特徴⑩
相続人や相続人の家族にクレーマー気質の人がいる

「クレーマー」と言うとちょっと言葉はきついですが、「どうしても自分が人より利益が多くないと「損」した気分になる」方もいます。
そんな方が、相続人や相続人の家族の中にいると、話し合いがまともに進みません。
元来、相続人の家族は権利者ではないので、話し合いに参加できないばかりか、その意思は尊重されないものですが、相続人の家族の意思に従ってしまう相続人が結構多いと感じます。
具体的に言うと、相続人の妻が、相続についてあれこれ調べてきて、相続人である夫に指示します。
税理士事務所では、「相続の相談」を受け付けるところもあります。
これは、「相続の相談」を受けることで新規顧客を開発するために行われています。
この「相続の相談」には、相続人本人ではなく、相続人の妻からの相談が非常に多いです。
しかも相続人当時者である夫には内緒の方が多いんです。
「自分は相続人ではない」と割り切れずに、自分の夫が少しでも有利になるよう、過去の出来事の恨みつらみをぶつける方もいます。
その夫もその指示にあった成果を上げないと、家に帰ってから妻に色々と言われるらしく、どうしても主張が激しくなります。
これは、嫁姑問題と似たところがあり、板挟みになっている相続人は、不幸でしかありません。
余談ですが、そういった方の「電話相談」は基本、丁寧にお断りします。
お断りする理由は、新規顧客につながらないというのが一番の理由ですが、それ以上に、当事者でないので相談内容が必ずしも正しいとは限らず、税理士事務所側も間違ったアドバイスをしてしまう可能性があるからです。
また、この逆も多くあります。
つまり、妻に相続があった場合です。
夫が今までのキャリアを基礎に、妻に「それは違う」などのアドバイスをします。
例えば、兄弟で穏便に話し合いが進んでいるときに、「もっと主張すべきことは主張しないとダメだ。」など、夫からのなんらかのアドバイスがあり、揉めてしまうことも多々あります。
このようにせっかく上手く話し合いが進んでいても、第三者が間接的にも介入しだすと、たちまち相続問題で揉めてしまいます。
このケースが「昔は仲のよかった兄弟」が揉めてしまう原因になります。
こういった場合、相続人がアドバイスをくれる家族にきちんと、「自分の家族(兄弟)のことに口出しするな。」と言って、一線を引くことが肝心です。
しかし、一線を引けば、自分が今暮らしている家族(配偶者や子)との歪がでてしまう危険性もあり、なかなかできません。
クレーマー気質の方が親族にいる場合は、被相続人がより一層対策を練っておく必要があります。
特徴⑪
相続人にお金が必要な人がいる

相続人にお金が必要な人がいると、相続で揉める可能性が高くなります。
もらった遺産でまかなおうと心情が働いてしまい、要求が多くなるためです。
お金が必要な人は、「借金がある人」に限りません。
例えば、
- 事業をしていて資金繰りが厳しい人
- 支払に追われている人
- 貯蓄が少ない人
- 子育て中でお金があれば助かる人
など、そもそも、「お金がいっぱいあっていらないよ」という人は少ないのではないでしょうか?
そのことからも、相続問題は誰にでも降りかかるトラブルと言っても過言ではありません。
相続人が揉めずに遺産相続するために被相続人がすべき対策

相続人が将来、相続で揉めることがないよう、被相続人が対策を講じておくことで、相続がおきても、相続人同士のトラブルを軽減できます。
- 弁護士に相談する
- 遺言書を書く
- 生命保険に加入する
- 普段から家族と話し合いをしておく
それでは1つ1つ見ていきましょう。
対策①
弁護士に相談する

相続で揉める家族の特徴に1つでも当てはまるものがあれば、必ず弁護士に相談しましょう。
市区町村にもよりますが、大体30分無料で相談にのってくれることがあります。
その他、「弁護士会」などでも30分~1時間で5,000円位で相談にのってもらえます。
もちろん財産が多い方は、こういった無料相談ではなく、キチンとした法律相談をお願いして下さい。
私は別件で法律相談を何回か受けたことがありますが、1時間1万円~1万5,000円前後で相談してもらえました。
一見高いと感じる方もいらっしゃると思いますが、一般人であれば、この金額で大体の悩みは解決します。
「法律的にはどうなんだろう?」とネットサーフィンしても得られる情報は限られています。
さらに、
法律はちょっとした違いでも結果が大きく変わるので、くれぐれも気を付けてくださいね。
どんなところで法律相談できるのかについては、「弁護士への法律相談で注意すること・相談場所がすべてわかる!」で詳しく説明しています。(気になる弁護士費用については「【誰でもすぐわかる!】弁護士報酬基準(費用)を徹底解説 」をご覧ください。)
相続の相談に行くときは、下記メモや資料を持っていくと話が早いです。
- メモ用紙・筆記用具
- 人物相関図(家系図)
- 財産一覧(もちろん簡単なメモでOK)
- 登記簿謄本(有料の法律相談では持参するように言われることがあります。)
法律相談の予約を入れる時は必ず、持ち物を確認して下さい。
「手ぶらでもいいですよ。」と言われても、上記のものはなるべく持参しましょう。
対策②
遺言書を書く

家族が揉めない一番の対策は、遺言書を書くことです。
遺言書には、大きく分けて「直筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
遺言書は、不備があると無効になります。
一般的には、「直筆証書遺言」が多いですが、「直筆証書遺言」は亡くなった際には、家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしなければならないため、残された相続人の手間がかかります。
またこの検認手続きで「署名がなかった」とか「○年○月吉日」というような日付になっていた場合は、書類の不備となり、遺言書の効力が無くなります。
さらに言うと、遺言書に不利なことが書いてあると思い、改ざんや隠ぺいされる可能性もあります。
できれば公証役場か弁護士に依頼することをおすすめします。
万が一、遺言を変更したい場合は、もう一度新しい遺言書を作成する必要があります。
遺産について遺言で意思を表明する場合は、「長男に○割」という「○割」ではなく、キチンと「○○銀行の預金○○円」と具体的に書きましょう。
固有の財産を示さず、割合で遺言してしまうと、現金化しやすいものを誰が相続するかで新たに揉める要因になってしまいます。
対策③
生命保険に加入する
生命保険に加入することでトラブル回避できる場合があります。
保険の受取人を多く財産をあげたい人にしてあげてください。
実は、保険金は遺産分割協議の対象外になります。
保険金は受取人の固有の財産となるため、遺産相続財産から除外されます。
たとえば、遺産が土地建物しかなく、兄弟で分け合えずに、「代償分割」で現金を他の兄弟に分けなければならないケースであれば、この死亡保険金を原資に他の兄弟に現金を渡すことができます。
また、面倒をみてもらったので、他の兄弟よりも多く財産をあげたい場合も、その子を受取人にした死亡保険に加入すれば、親が死亡した際、相続人の同意がなくてもすぐに保険請求をし、受取人は保険金を受け取ることができます。
さきほども少しお話ししましたが、この保険金は法律的には相続財産ではないので、他の相続人には手出しできません。
よって、特定の子に多く財産をあげたい場合はとても有効な手段です。
また、長男に面倒を見てもらっていたが、折り合いがつかず、次男に面倒をみてもらうことになり、遺産を多くあげたい子が変わっても、保険であれば受取人を簡単に変更することができます。
例えば、「家を長男にあげるから保険金を次男に」という思いだけで契約してしまうと、(保険金は相続財産にならないため)次男が保険金を手に入れ、さらには家の権利を主張することができてしまいます。
よって、「平等に」との思いとは裏腹に、次男に財産が多く渡ってしまう場合があります。
相続問題に有効な保険は、ズバリ、「一時払い終身保険」です。(詳しくは「【相続対策で有効な生命保険】一時払い終身保険のメリット・デメリット」で記載しています。)
今では、無料で保険相談にのってくれるところがあります。
自宅で相談もできますし、自宅で相談しづらい場合は、店舗や喫茶店でも相談にのってくれるのでおすすめです。
ここではおすすめの保険相談窓口をピックアップしました。
|
マネードクター
|
保険チャンネル
|
保険見直し本舗
|
保険見直しラボ
|
保険マンモス
くわしく見る |
保険ガーデン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗相談 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 訪問サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○(電話相談も可) | ○ | - | - |
| 生命保険 | ○(22社) | ○(14社) | ○(24社) | ○(21社) | ○(店舗による) | 派遣される FPによる |
| 損害保険 | ○(10社) | ○(14社) ※ペット保険2社含む |
○(13社) ※ペット保険2社含む |
○(11社) | - | 派遣される FPによる |
| 公式HP | |
 |
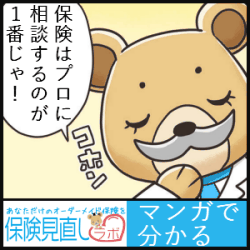 |
 |
 |
こちらからすぐに相談を申し込めるので、気になった保険窓口相談があったら申し込んでみて下さいね。
保険の窓口についてはこちらの記事を参照して下さい。
相続対策は専門性が非常に高いので、優秀なFPが多い、マネードクターがおすすめです。
ただし、コンタクトを取る際は必ず、「相続に強いFPを」とリクエストして下さい。
<公式>マネードクター
★家族に内緒でこっそり相談したい方は【アプリ】で相談できます。(チャット形式)
★保険の見直しには下記アプリで簡単にアドバイスがもらえます。
\ 無料で診断! /
- 何回でも利用可
- 住所・氏名・電話番号などの個人情報不要
- 希望があれば相談にものってもらえる
パシャって保険診断については下記で詳しく記載しています。
対策④
普段から家族と話し合いをしておく
普段から家族とよく話し合いをしておくことも有効です。
ただし、相続人の一部と話をしても意味がありません。
たとえば、子が2人いた場合、そのうちの1人と「お前には土地建物をやるから、現金は他の兄弟に相続させてくれ。」と話しても、かえってトラブルになるだけなのでやめましょう。
話し合いをする場合は、相続人全員で集まってするのが絶対条件です。
ただし、この話し合いにより、家族関係が崩れることもあります。
ですので、家族間の話し合いでは、お互いの要望を聞くだけの「場」にして、ご自分で相続についてキチンと決めることが、トラブル対策になります。
「決定事項は被相続人が決めた」と相続人が納得すれば、誰も口出しできません。
どういう結果であろうと、すべては被相続人の責任下において行えば、相続人同士の心のわだかまりは少なくなります。
まとめ:相続で揉める家族の特徴に1つでも心当たりがあったら、早めの対策を!

相続については、実は、「みんなが円満に」ということはほぼありません。
また、1つの相続が終わって、次の相続が発生した際に、1つ目の相続の残っていた私恨が再発する事例も見てきました。
そういった、争いを避ける方法は1つしかありません。
それは、被相続人がキチンと財産整理をしておくことです。
まだまだ、若い気でいらっしゃる方もいますが、そういう方の多くは、「そのうち考えよう」と問題を先延ばしにしています。
病気になった際、余命宣告をされた場合は、まだ、整理の時間も持てますが、急な不幸が襲ってくることもあります。
何も遺産について整理してなければ、遺族である相続人は、急な不幸で悲しみの中、遺産トラブルに対応しなくてはならず、大変な思いをします。
今回ご紹介した、「相続で揉める家族の特徴」に1つでも思い当たるものがあれば、「そのうち」ではなく「すぐに」でも行動しましょう!
- マネードクターの評判(口コミ)は?|デメリットや疑問点を【体験談から】徹底解説!
- 「必要な保険は3つだけ」は本当?|最低限入っておくべき保険と理由を解説
- 【保険の窓口にカモられるかも!?】騙されないための7つの方法
- 【遺産相続】相続税っていくらまで無税?|いくらから税金かかるの?
- 相続税は自分で申告しない方がいい理由と税理士の選び方6選
- 【生命保険の受取人がいない人も必見】保険金を親族以外に遺贈する方法
- 【注意】110万以下の贈与でも非課税にならない場合がある!
- 【無料保険相談のカラクリを暴露】 利益の構造(からくり)を知ってかしこく相談!
- 【保険見直し本舗のデメリット5つ】「しつこい」って評判は本当?|ほけんの窓口との比較も掲載
- ほけんの窓口のもうけのからくりは?|無料の保険の窓口のデメリットも紹介
- 【直営店の見分け方も記載!】ほけんの窓口「評判は最悪?」|実際に相談して検証















